
目的地を決めることが、AI活用の第一歩

システムエンジニアとして働く傍ら、ITスクールの講師や、AIを使った業務改善に取り組んでいる鈴木孝幸(すずき たかゆき)さんの連載コラム第1弾です。AIを使えば作業は早くなるはずなのに、「思ったほど成果が出ない」と感じたことはありませんか?本記事では、AI活用の第一歩として欠かせない「目的地を決めること」の大切さをお伝えします。
AIは本当に便利です。
調べ物から資料作成、アイデア出しまで、僕も毎日のように助けられています。
作業時間が半分、あるいは三分の一になることも珍しくありません。
けれど一方で、「思ったほど成果が出ない」と感じる場面もあります。
その原因は、AIの性能やプロンプトの問題なのでしょうか?
最初に目的、目標を決めること
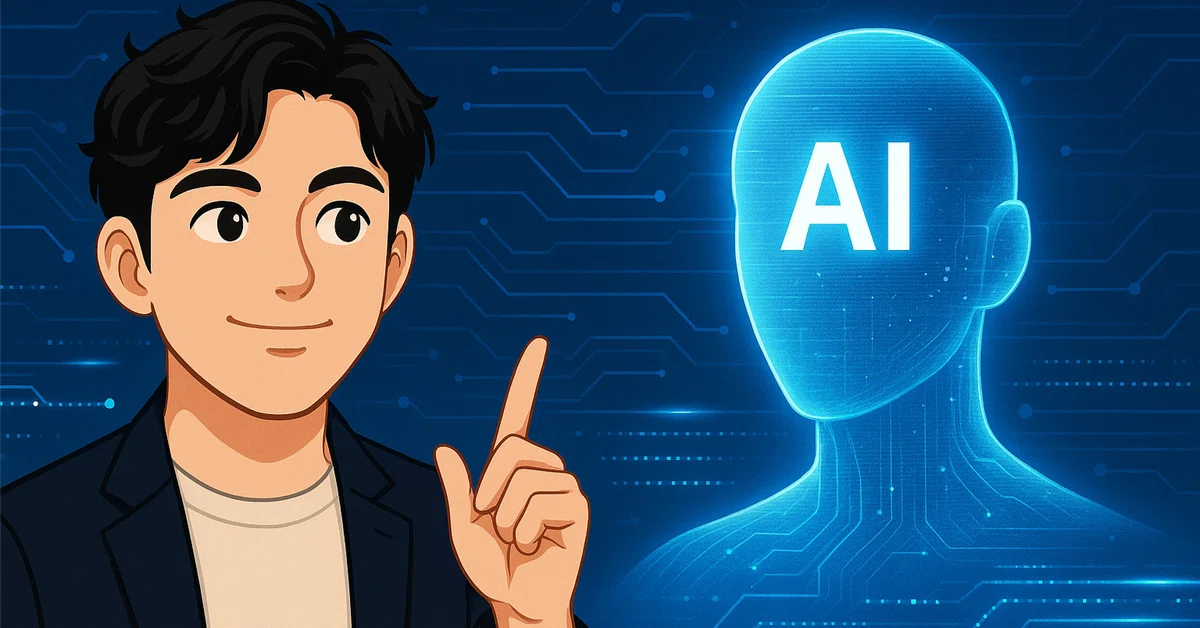
「思ったほど成果が出ない」という問いに対して、僕がよく思い出すのはワクセルでいつもお世話になっている総合プロデューサーの住谷知厚さんの言葉です。
だいたい僕が迷っているときには、「まず目的、目標を決めよう」と声をかけていただいて、ハッと我に返ります。
※しょっちゅう迷っているのはここだけの話です笑
目的や目標を持たずに動くと、やっていること自体は忙しいのに、気づけば迷走している。
誰かに与えられたレールの上を走るしかなくなって、自分で選んでいる感覚を失ってしまうんです。
だからこそ「自分で目標を決める」ということが大切だと、いつも実感しています。
このことについては、住谷さんご自身もインタビューで語られています。
https://sumitanitomohiro.jp/index.php/20schallenge/
目的がないと迷走する理由

目的地が定まらないと、どんなに性能が高いAIでも成果は出ません。
Googleマップを想像してみてください。
目的地を入力しなければ、最短ルートは表示されませんよね。
AIも同じで、ゴールが決まっていなければ、答えはどうしてもぼんやりしたものになります。
そしてAIは新幹線のような存在でもあります。
速くて快適で、正しく使えば一瞬で遠くまで運んでくれる。
ただし、目的地が決まっていなければ、新幹線が適切かどうかはわかりません。
近所のスーパーに行くのなら、自転車や徒歩の方が合理的です。
目的地を決めずにただ乗っていると、気づいたら別の街に降りている。
AIも同じで、道具そのものの良さに振り回されないためには、まず行き先を定めることが必要です。
ツールの選び方は目的次第

目的が決まれば、自然とツールの選び方も見えてきます。
・調べ物をしたいなら、欲しい答えが出るまでChatGPTやGemini、Feloに何度か質問を重ねる
・スライド作成を効率化したいなら、Gensparkにやってもらう
・単純な繰り返し作業を効率化したいなら、RPAツールを導入するのが有効な場合もある
・自分の思考力を鍛えたいなら、そもそもアナログに紙とペンで自分の手を動かして考える時間を取ることが最強かもしれません
→このテーマは次の記事で深堀します。
要は【目的地が先で、ツールは後】
ツール先行で始めてしまうと、効率的に見えて実は迷走しているだけ、ということになりかねません。
人間にしかできないこと

目的地を決めるのは、人間にしかできないことです。
AIは目的に向かうための強力な道具であり、うまく使えば最高の相棒になります。
だからこそ、胸を張って言いたい。
AIをどう使うかは、あなた次第です。
ただの便利ツールにするのか、自分の成長や挑戦を後押ししてくれる相棒にするのか。
あなたは、何のためにAIを使いますか?
その問いに自分なりの答えを持てたとき、AIは本当の意味で味方になってくれるかもしれません。
ぜひnoteの記事とInstagramも見てみてください。





