
AIを封印する時間が「思考の基礎体力」を鍛える

システムエンジニアとして働く傍ら、ITスクールの講師や、AIを使った業務改善に取り組んでいる鈴木孝幸(すずき たかゆき)さんの連載コラム第2弾です。AIの進化で、私たちの仕事や暮らしは驚くほど便利になりました。その一方で、「考える力」や「感じ取る力」が少しずつ失われているのかもしれません。便利さの先にある「人間らしさ」とは?本記事では、これからのAI時代に必要な人間力についてお伝えします。
AIって、本当に便利ですよね。
質問を投げればすぐに答えが返ってくるし、これまで何時間もかかっていた作業が一瞬で終わる。
メールを書いたり、会議のメモをまとめたり、企画のアイデアを出したり..僕も毎日のようにAIに助けられています。
でも、任せっぱなしにしていると、自分の頭を使う時間がどんどん減っていく。そんな感覚を覚えることがあるんです。
たとえば、パソコンやスマホに頼りすぎて、いざ漢字を書こうとすると「あれ、どう書くんだっけ?」って手が止まることありませんか。
読み方はわかるのに、文字にしようとすると思い出せない。便利さに支えられる一方で、確実に失っている感覚もある。
AIとの付き合い方によっては、似たような危うさを抱えるんじゃないかなと僕は思うんです。
ツールは次々に現れる

僕はシステムエンジニアを15年やってきました。
AIに限らず、これまでも便利なツールは次々に登場してきました。自動化スクリプト、クラウドサービス、プロジェクト管理ツール…
そのたびに「これで仕事が楽になる!」と喜んできたし、実際に効率も大きく上がった。
けれど一方で、便利さに甘えすぎて、思考の基礎体力が弱っているな…と感じる瞬間もあったんです。
子供の頃からの弱点
自分は子供の頃から、よく「詰めが甘い」と言われてきました。
テストで凡ミスをしたり、最後の確認を怠って失敗したり。社会人になってからも、この弱点は未だに抱えています。
だから「このツールを使えば克服できるかも?」と色々試してきたんです。チェックリストのアプリやマクロ、自動化の仕組み…
でも結局、一番頼りになったのは、当時の先輩から言われた紙に印刷してペンで書き込みながらチェックするやり方でした。
アナログだけど、紙にすると「あれ?」と自然に引っかかる。画面ではスルーしてしまうミスも、紙にすると気づける。
僕にとっては、この“紙とペン”が最後の砦みたいな存在なんです。
ときにはあえてAIを封印する理由

だから今でも、AIを使いながら、あえて封印する時間を持つようにしています。
アナログチェック以外にも、いくつか意識してやっていることがあります。
・紙の本にマーカーを引き、汚しながら読む
・紙に図や箇条書きを書き出す
・同僚や友人に考えをアウトプットする
・書いた文章を音読する
どれも手間はかかりますが、この“ひと手間”があるからこそ、より考えが深まったり、新たな視点によって気づくことが多いのだと思います。
ここで強調しておきたいのは、アナログとAIの優劣をつけたいわけじゃないということです。
新しいものを受け入れつつ、その人に合ったやり方を模索していく。
その姿勢こそが大事なんじゃないかなと僕は考えます。
思考の基礎体力を鍛える
AIを上手に使うには、実は「AIを使わない時間」が必要なんだと思うんです。
僕たちが思考の基礎体力を持っているほど、AIの出力をちゃんと評価・判断できる。
自分でまとめる力がないと、AIの答えをそのまま信じ込んでしまう。
それって危ないですよね。気づいたらAIに支配される一歩手前。
自分の意思を持たずに機械に従うのは、ただの思考停止だと思います。
だからこそ、日常の中で思考の基礎体力を鍛えておくこと。
これがAI時代を主体的に生きるための武器になるんだと、僕は考えています。
AIは相棒
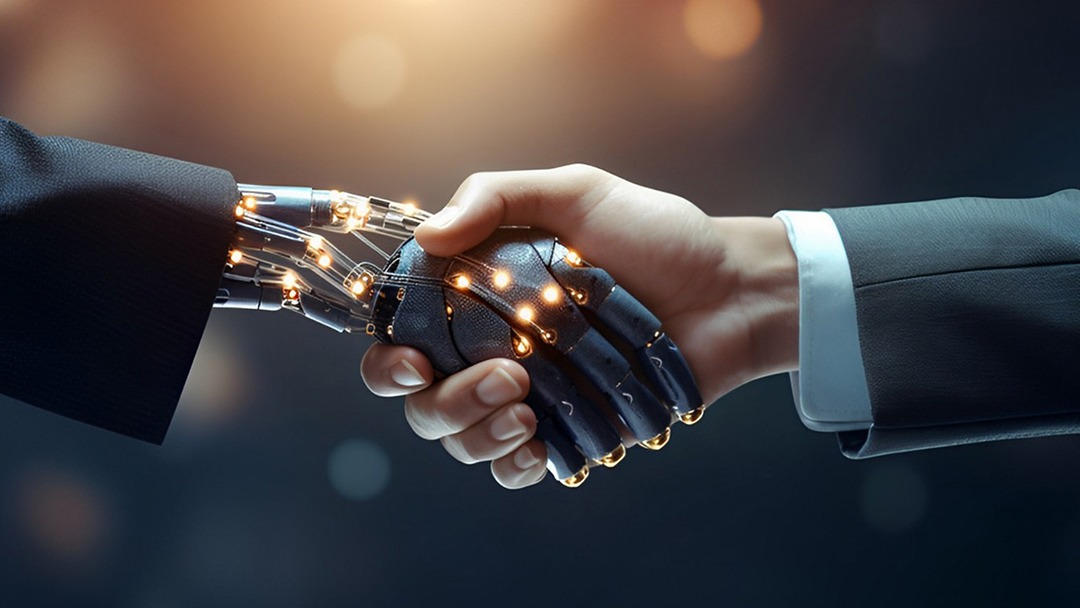
「じゃあAIは危ないの?」って聞かれたら、僕はそうは思いません。
AIは敵じゃない。
むしろ、正しく使えば人間の可能性を広げてくれる最高のパートナーです。
ただ、その力を引き出せるかどうかは、人間側の準備次第。
思考の基礎体力を持っている人ほど、AIを使いこなせる。
依存するんじゃなくて、協力する。
そんなスタンスでこれからも向き合っていきたい。
AIはあくまで相棒。最後にハンドルを握るのは、やっぱり自分たち自身なんだと思います。
SNSでシステムエンジニアとしての経験からAIに関する投稿を行っていますのでぜひ見てみてださい!
ぜひnoteの記事とInstagramも見てみてください。





