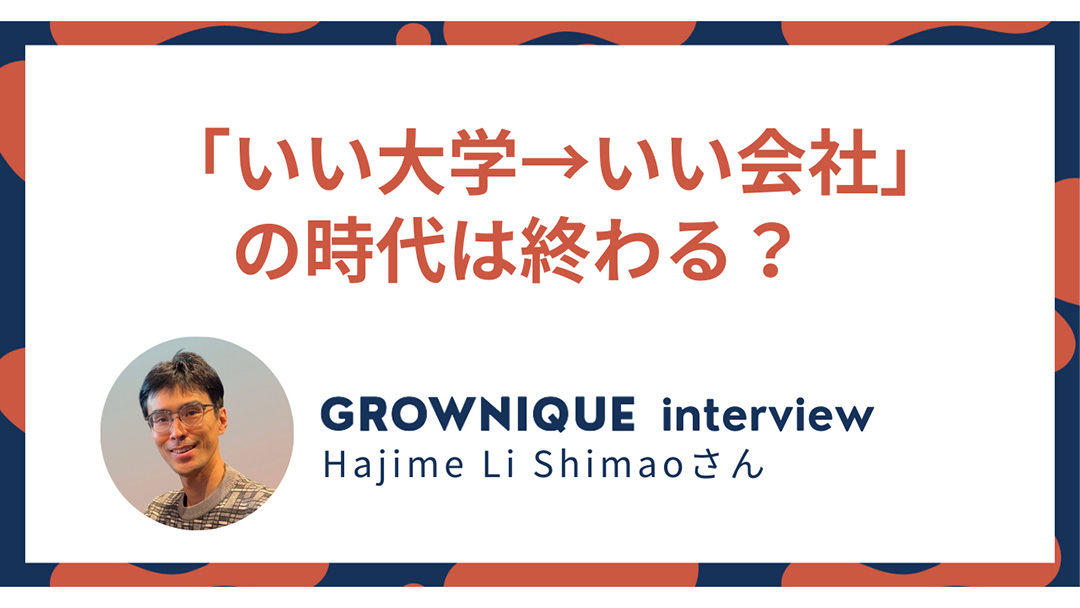多分野を横断するアメリカの大学助教に聞いてみました!【GROWNIQUEインタビュー】
はじめに
グローバル化、デジタル化が急速に進む現代社会では、これまでの「正解を選ぶ」教育から「自ら問いを立てる」教育へのシフトが求められています。
今回は、アメリカで経済学、ファイナンス、法学、教育学など広範な社会科学を横断し、データアナリティクスとAIの応用研究を行っているペンシルバニア州立大学助教 Hajime Li Shimaoさんにお話を伺い、未来を見据えた教育のあり方を探ります。
家庭で実践できる未来志向の教育法や、これから学ぶべき注目分野について具体的なヒントをお届けします。
1. 「正解」よりも「問い」を育む教育とは
島尾さんは、「教育→就職→収入」という従来のフレームを一度忘れることが重要だと語ります。これからの時代、労働市場での競争力よりも、「人生を豊かにするため」の教養を育むことが大切だといいます。
「今からプログラミングやSTEM教育を学んでも、20年後にはホワイトカラーの仕事そのものが少なくなっているという見方も十分ありえます。そもそも学校教育が労働市場で必要なスキルに直結するものという考え方は、産業革命以降に生まれた比較的最近のものです。」(島尾さん)
島尾さんは、教育の本来の目的は人生を豊かにするための教養を育むことにあると指摘します。特に、好きなことを見つけ、それを深める力が重要だと述べています。
「勉強を『将来役に立つから』とか『楽に生活できるから』といった視点で考えるのではなく、子どもが好きなことを見つけて学ぶことに時間を使うことが望ましいかもしれません。」(島尾さん
2. 家庭でできる!学びの土台作り
家庭で実践できる教育法として、島尾さんが強調するのは、意思決定力や考える力を育む取り組みです。以下のポイントが挙げられます:
説明を惜しまない
子どもの年齢に合わせて、丁寧に説明する習慣を持つことが大切です。単に簡潔に伝えるのではなく、背景にある科学や論理も含めて説明し、子どもが納得できるようにすることが、考える力を育てます。また、できるだけ自分で意思決定させることも重要です。島尾さんは、お子さんが2歳の頃、お風呂に入りたがらなかった際に、納得できるまで説明を続け、最終的に2時間かかったこともあるそうです(!笑)。
例1:
「たとえば、『なぜ落ちているものを食べてはいけないのか」に対して、『落ちてるものは食べちゃダメ!』、『落ちてるものを食べるとお腹痛くなるよ』ではなく、『1ミリの1/300とかの大きさだから目では見えないけど、落ちてるものには体に悪い菌がついていてそれが体の中で繁殖するとお腹が痛くなるよ』まで説明します。」(島尾さん)
例2:
「『ユニコーンは産まれたとき、何センチ?』と聞かれたら、『分からないから他の生き物で考えてみようか。見た目もサイズも馬っぽいから、馬と同じなら1mくらいかな?でもツノはどうなっているんだろうね。生まれたときからツノが生えていたら、お産のときママが痛そうだね。ツノのある動物、ヘラジカとかを考えてみると、やっぱり最初はツノがなくて段々生えてきてるね。ツノはオスにしか生えないのかな?メスにも生えるのかな?どうなんだろうね。まあ、とりあえず、馬のお産の動画をYouTubeでさがしてみようか。』といった感じで返します。」(島尾さん)
自由な問いかけを奨励する
たとえば、家族のごっこ遊びでは、リアリティと独創性を求めます。「道具を知らない星から来た人を想定して地球の物を説明する」など、想像力を刺激しながら論理的に考える訓練につながる遊びを提案。
親のディスカッションを見せる
親同士が理性的なディスカッションを行う姿を隠さずに見せることも、子どもにとって大きな学びになります。質問されたら、背景まで含めて説明する姿勢が鍵です。
「『子供にはまだ早い』みたいに甘く見ないで、最初から何でも投げてみるという姿勢が大切かもしれません。」(島尾さん)
3. これからの時代に必要な学びとは?
島尾さんは、現代の親たちが注目するSTEM教育やAI、プログラミングといった分野について次のように述べています。
「20年後の未来では、プログラマーがAIに取って代わられている可能性は非常に高い。しかし、CEOのような意思決定を行う仕事がAIだけに任される可能性は低いと思います。それに、結婚や転居といった自分の人生のための決断は、AIのアドバイスがあったとしても結局は自分自身がする必要があります。そのため、意思決定力を鍛えるための教育の価値が今まで以上に高まると思います。」(島尾さん)
また、文学や歴史などの人文系や芸術分野の価値が再評価される時代になるとも指摘しています。これらの分野は、単なる労働市場への適応だけでなく、人生をより豊かにする基盤を提供してくれるものです。
さらに、家庭内で「これがどう役立つか」を一緒に考える習慣を持つことも重要だといいます。
「好きなことを軸に学ぶ分野を選ぶと、子どものモチベーションも上がります。その中で、創造性や論理的思考を伸ばせる環境を整えてあげることが大切です」(島尾さん)
終わりに:子どもの未来は、家庭からひらく
未来志向の教育は、学校だけではなく、家庭内での関わり方からも始められます。親として子どもにどのような環境を提供できるのかを見直し、新しい時代にふさわしい教育の形を模索してみてください。
家庭での実践が、子どもの未来を切りひらく第一歩となります。私たち大人自身が学び続ける姿勢を見せることも、子どもにとっては大きな刺激になります。日々の生活の中で、「一緒に考える」「一緒に学ぶ」という視点を持ちながら、未来を切りひらく力を育む、子どもたちの未来を輝かせる鍵となるはずです。