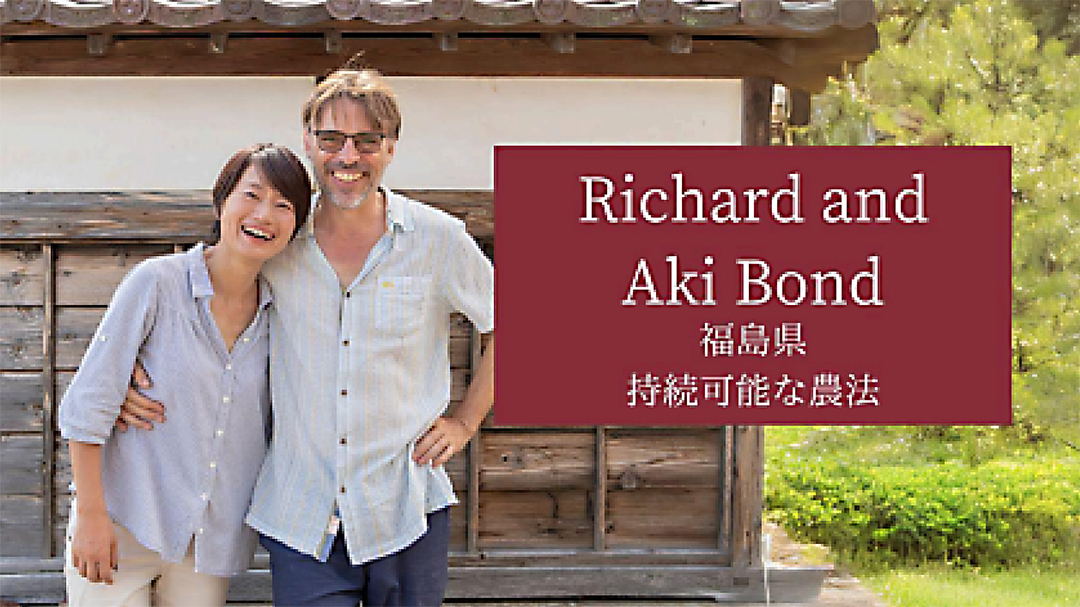江戸時代のエナジードリンク「甘酒」が、いま日本人を救う!?
「甘酒」と聞くと、冬の神社でいただくほっとする一杯や、どこか懐かしい発酵食品のイメージを持つ人も多いだろう。だが実はこの甘酒、江戸時代には夏の栄養ドリンクとして絶大な人気を誇っていたことをご存じだろうか。猛暑で疲れ果てた庶民が、道端で売られる甘酒をゴクゴク飲んで体力を回復していた、まさに当時の「エナジードリンク」だったのだ。
そんな甘酒のチカラを、現代の食卓に新しい形で蘇らせようとしている人物がいる。
彼女の名は町亜由美さん。甘酒を「ふりかけ」にすることで、子どもから大人まで手軽に取り入れられる商品を開発し、多くの人に“発酵の恵み”を伝えている。なぜ彼女は甘酒を現代に広めようと考えたのか。そして考えたのが「粉末にする」、その取り組みがもたらす家族や社会への影響はどのようなものなのか。町さんへのインタビューを通じて見えてきたのは、日本の伝統と現代のライフスタイルを見事に融合させた、健康と絆の物語だった。
きっかけは「子どもたちを健康にしたい」という母の思い
町さんが「甘酒ふりかけ」を開発するに至った最大のきっかけは、自身の子どもたちを思う“母の愛”だったという。
「サッカーの練習の後、子どもたちが疲れ果てている姿を見て何か自然な方法で栄養を補給できないかなって考え始めたんです。最初は市販のゼリー飲料を持たせていたのですが、裏ラベルを見たら添加物がたくさん入っていて。これを飲ませ続けるのはどうなんだろう、と不安になりました。」
そこで思い出したのが、幼い頃に飲んでいた甘酒だ。ちょうど発酵食品のリサーチをしていた彼女は、甘酒がかつて「夏バテ防止」に重宝されていた事実を知る。それはまさに、江戸の人々が暑さで消耗した身体を甘酒で癒していたという、歴史上の名場面でもあった。
「子どもたちの体力回復にぴったりじゃないかって思ったんですよね。腸の健康にも良いし、何より自然な甘みがあるので、子どもでも抵抗が少ないかもしれないって。」
こうして彼女は、甘酒を日常に取り入れるための方法を模索し始めた。ところが実際には、子どもに飲ませようとすると「ちょっとクセが強い」「毎日は厳しいかも」という声が家族から上がった。そこで考えたのが「ふりかけ」という形にしてしまうこと。粉末状にすることで、料理にも混ぜやすくする工夫を思いついたのだ。
息子が語る「甘酒ふりかけ」の効果と母への感謝
実際に、町さんの息子は「甘酒ふりかけ」や「甘酒の粉」を活用した食生活によって、コロナ禍を健康的に乗り越えることができたと語る。
「コロナ期間中でも、母が毎日、甘酒の粉をいろんな食事に入れてくれたり、甘酒ふりかけでおにぎりをつくってくれていたおかげで、病気らしい病気にならずに過ごせたんです。正直、最初は甘酒の独特な味が苦手で『ウィダーインゼリーのほうが気軽じゃない?』って思ってました。でも父を含め、家族みんなが最初はあまり乗り気じゃなかったからこそ、母が粉末やふりかけにしてくれた。そうすることで自然と食事に取り入れられるようになりましたね。本当に感謝しています。」
最初こそ「甘酒って飲みにくい」「ゼリー飲料のほうが良い」と思った息子だったが、母の工夫によって食事にさりげなく組み込まれ、いつしか抵抗なく甘酒の恩恵を受けられるようになったという。この成功体験があったからこそ、町さんは「家族みんなで楽しめる形」を追求し、ふりかけの商品化に情熱を注いだのだろう。
代々続く田園調布暮らしと”サザエさん一家”のような日常
町さんのご家族は、寛永元年(1624年)頃から田園調布に住み始めたという長い歴史を持っている。まさに「代々ここに根を張って生きてきた」一族だ。四世代同居でサザエさん一家のように大家族が当たり前。日々の食卓には常に味噌汁や漬物など日本の伝統的な家庭料理が並び、外食はほとんどしない生活だった。
「小さい頃から味噌や醤油、漬物など、自家製の発酵食品が当たり前にある暮らしでした。外食ってほとんど経験なかったので、大学生くらいになってファミレスに行ったときは、正直ちょっとショックでしたね。『こんなに添加物が入っている食事って、身体に良いのかな……』っていう違和感が大きくて。」
町さんにとって、自然由来の食材を使い切る「もったいない精神」は、幼いころからずっと身近な存在だった。だからこそ、家族の健康を守るために甘酒を活用することには、何の抵抗もなかったのだろう。むしろ、先祖が培ってきた伝統を現代の環境に合わせてアレンジする“楽しさ”すら感じていたようだ。
甘酒ふりかけに込められた「江戸の知恵」と「現代の工夫」
甘酒には大きく分けて2種類ある。酒粕を使ったアルコール入りタイプと、米麹を使ったノンアルコールタイプだ。町さんが選んだのは、子どもにも安心して口にしてもらえる米麹甘酒。そこには、江戸時代から続く「発酵の力を日常に取り入れる」知恵が詰まっている。
ただし、甘酒を粉末にする際には栄養が損なわれるリスクがある。そこで町さんは、「低温乾燥技術」という方法を使って、甘酒本来の酵素やアミノ酸、ビタミンを最大限に保つ製造法を導入した。
「せっかくの栄養が加熱で壊れたらもったいないですからね。だからこそ、低温でじっくり乾かして粉にする。この一手間が、うちの甘酒ふりかけの大切なポイントなんです。」
さらに、子どもやアレルギーを持つ人に配慮して化学調味料を使わず、アレルギーに配慮した原材料を選ぶなど、細部までこだわりを貫いた。味付けもシンプルにして、ご飯にかけるだけで飽きずに食べられる味わいに仕上げている。
いかがだったでしょうか? 江戸時代、暑さに打ち勝つための庶民の「元気の源」として親しまれた甘酒。その伝統が、現代のライフスタイルに合わせて“甘酒ふりかけ”という新たな形で甦ります。町さんが手掛けるこの商品は、単なる健康食品ではなく、家族や地域の絆を深める文化活動へとつながるストーリーが詰まっています。この記事の続きは株式会社えんむすびのHPでご覧になれます。
【完全版】江戸時代のエナジードリンク「甘酒」が、いま日本人を救う!?
https://enmusubi.company/2025/01/31/amazake
インタビューを受けてくださった町あゆみさんについて
東京で4世代同居で育ち、和食や発酵が当たり前な学生時代を過ごす。上場企業の役員秘書を3年したのち、体調を崩して退職。
健康への関心と趣味だった料理を生かし、料理教室にて5年働く。出産後専業主婦となり、製菓衛生師、発酵食品ソムリエの資格を取得。
2014年、夫が脱サラしインターナショナル保育園を開いたのを機に保育園給食、五感を育む食育をはじめ11年目。現在は発酵グルテンフリーの給食提供をしている。
2020年、試行錯誤した糀甘酒のパウダー化が実現し、糀甘酒のパウダーを加えた『甘酒ふりかけ』の販売を開始。2025年 『糀甘酒パウダー』特許取得。
家庭の食卓を笑顔に!をモットーに活動している。いつか保育園のグルテンフリーレシピ本を出すのが夢!
甘酒ふりかけは、糀甘酒パウダーをベースに、さまざまな風味を加えたふりかけ。ご飯やおにぎり、サラダにかけるだけで手軽に発酵食品を取り入れられます。
「もっと手軽に、もっと美味しく、もっと健康に!」
あゆみの甘酒は、毎日の食卓を豊かにし、家族みんなが笑顔になれる味わいをお届けします。