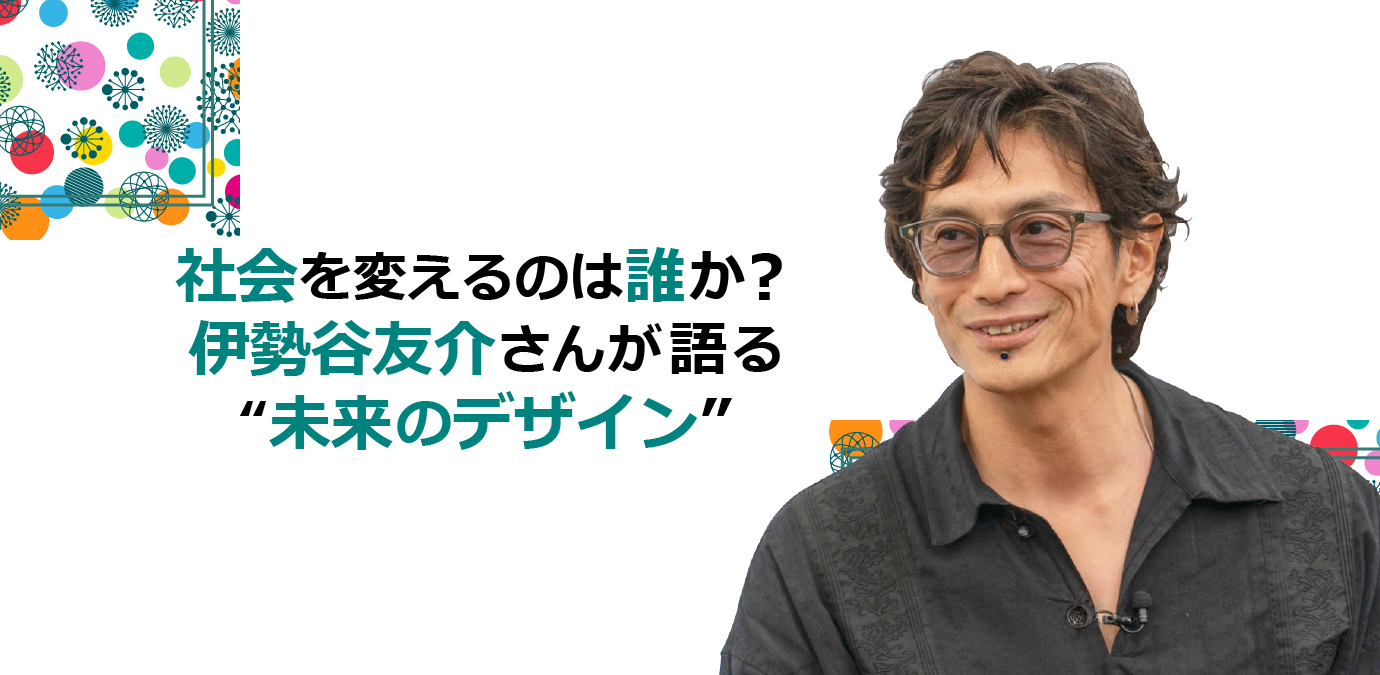
俳優、映画監督、実業家
伊勢谷友介 × 住谷知厚
俳優、映画監督、そして実業家。多彩な肩書きを持つ伊勢谷友介(いせやゆうすけ)さんは、表現者としての枠を超え、社会そのものをデザインする存在として注目を集めてきました。 東京藝術大学で培った美術とデザインの視点、俳優として現場で鍛えた表現力、そして「人類が地球で生き残るためにはどうすべきか」という根本的な問いに立脚した社会活動。 そのすべてが伊勢谷さんの思考と行動に一本の軸を与えています。 今回のトークセッションでは、伊勢谷さんがなぜ“社会を変えること”にこだわるのか、その背景にある思考や経験に深く迫ります。 教育、起業、芸術、幸福論、そして吉田松陰から受けた影響まで、多角的な視点で語られる言葉のひとつひとつに、未来をつくるヒントが詰まっています。
自分の幸せの定義と、社会を変革する理由
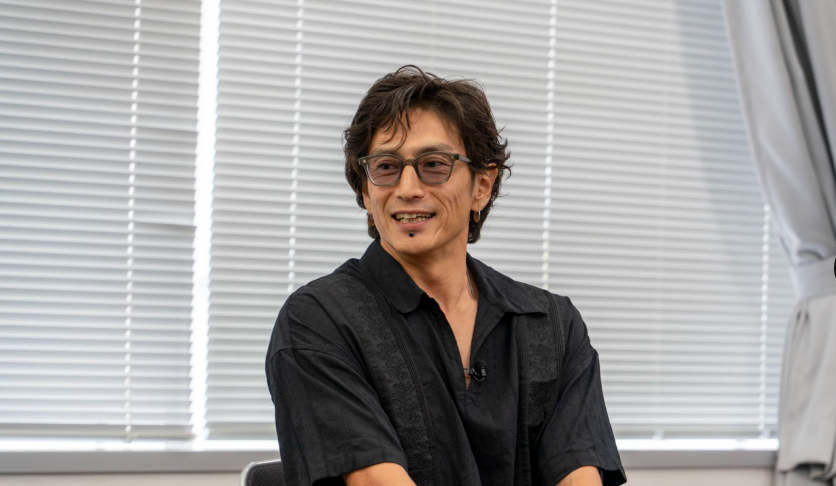
伊勢谷:もともと僕は東京藝術大学のデザイン科で、現代美術を学んでいました。 その過程で、映像表現の中でも特に映画というメディアが、もっとも人に強く訴えかけられる手段だと気づいたんです。 120分間、暗闇の中で集中して観てもらえる。その贅沢な時間を使えることが映画の魅力でした。 最初は監督を目指していて、そのために俳優を始めたんです。俳優は、現場で一番監督から演技指導を受ける立場だと思い、勉強になると思って飛び込みました。 バイトでモデルもしてましたね。たまたまオーディションに受かって、そこから俳優としてのキャリアが始まったという流れです。
住谷:映画から事業にシフトしたのはなぜでしょうか?
伊勢谷:僕は“社会変革”がしたいだけなんです。その手段が映画だけでなく、企業活動にもなったということ。 株式会社という仕組みを使えば、自分たちの思想やビジョンを商品やサービスに乗せて広められる。 それに気づいたとき、「これは社会を動かせるかもしれない」と本気で思ったんです。
企業活動に取り組んでいくなかで、どんどん人の力を借りて形になっていくのを体感しました。 「こういう社会課題がある。だったらこういうアプローチで解決できるかもしれない」と話し合う時間が、僕にとっては最高に幸せな瞬間でしたね。 だからこそ、プロジェクトを立ち上げるときも、個人のスキルや想いが最大限発揮できる形を目指しています。
デザイン思考と種の存続

伊勢谷:僕がよく話すのは「デザイン思考」というものです。芸大のときから一貫して考えていることなんですけど、人間は「目的」を設定してから、それに最適な「手段」を選ぶんですよね。 そのとき大事なのが「なぜ自分は生きているのか」という問い。カエルも、アメーバも、バクテリアも生きる目的って全部“種の存続”じゃないですか。 だから、人間もその延長線上で考えるべきだと思ってるんです。生きることに“理由”があるなら、それは人類全体としての存続をどう実現するか、という視点になるはずです。
住谷:かなり大きな視点ですね。
伊勢谷:ええ、でも簡単な話なんですよ。「どう生きたいか」と考える前に、「人類がどう存続していくか」を起点に考えてみる。 その未来像から逆算して、自分はどういう存在でいたいのか。そこから社会設計していくのが僕の考えるデザイン思考です。 たとえば、AIやテクノロジーが進化していく中で、僕たちの社会が「便利」になる一方で「幸せ」が遠のいているように感じることもあります。 便利さと幸福は必ずしも比例しない。だからこそ、種の存続という大きな視点から、どうすれば社会が調和していけるのかを考える必要があると思っています。 今の資本主義社会って、どうしても「お金が目的」になりやすい。それが悪いとは言わないけど、気がつくと自分が何のために生きていたのか分からなくなってしまう。 だから「目的を忘れないこと」がものすごく重要だと思っています。 さらに言うと、「教育」のあり方にも課題を感じています。今の日本の教育は「正解」を教えることに重きが置かれすぎていて、“目的を見つける力”を育てるような機会が圧倒的に足りていない。 だからこそ僕は、教育の現場にも関わっていきたいと思っているし、思考を深めるための高校設立にも携わってきました。
命をどう使うか――吉田松陰から学んだ生き方のヒント
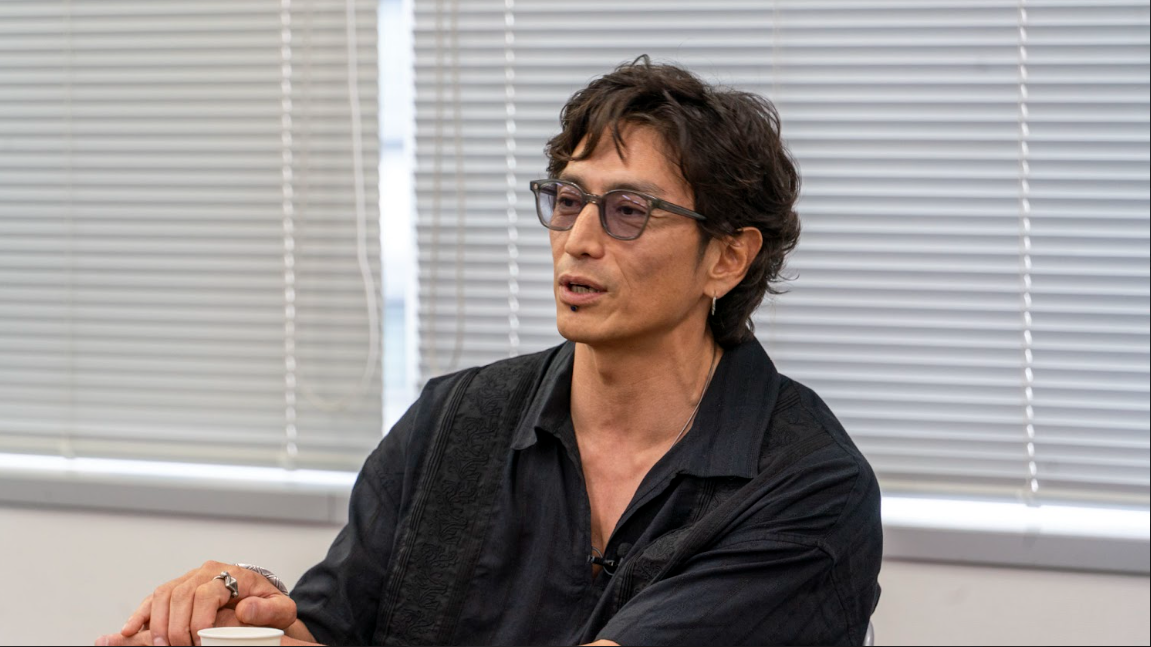
伊勢谷:僕が俳優として演じた役のなかでも、とりわけ心に深く残っているのが「吉田松陰」なんです。 大河ドラマ『花燃ゆ』で演じたんですが、彼の思想や生き方に触れたことが、僕自身の人生観に大きな影響を与えました。 吉田松陰というと、幕末の過激な思想家、テロリスト的なイメージを持たれることもありますが、僕はそう捉えていません。 彼は、自らの命をかけて「未来のために何ができるか」を考え抜いた人です。 実際、彼が処刑されたのは29歳。僕がちょうどその年齢に差しかかっていたころ、その事実に圧倒されました。 まだ何者でもなかった自分と、国の未来を託される志士として死を選んだ彼の姿が重なって、命の重みを改めて実感しました。 彼は自分が監獄に入れられたあとも、塾(松下村塾)を開き、思想を若者たちに伝え続けました。 身分の上下関係を超えて、真剣に語り合い、未来を描こうとした。 伊藤博文、高杉晋作など、明治を切り開いた人材がその場から育ったということが、その結果です。 単なる「偉人伝」ではなく、「社会変革の連鎖」として受け取ったとき、そのエネルギーに心を動かされました。
住谷:まさに、命の使い方を問われるような存在だったんですね。
伊勢谷:そうなんです。彼の生き方は、現代の僕たちにも通じる部分があると思っています。 今、社会に対して不満や課題を感じている人は多いけれど、「だからこそ自分が行動するんだ」と命を燃やして生きる人は多くない。 吉田松陰は「死んでも伝えることがある」と考えた。その覚悟がすごいんです。 現代社会では“死”を避けることばかりが重視されがちだけど、命を守るために何をするか、命をどう使うかという発想も必要だと思っています。 僕は、彼のように命を投げ打ってでもやる覚悟までは持てていないけれど、自分ができる範囲で、社会の仕組みを変えることに挑戦し続けたい。 だからこそ、自分にとっての“幸せ”を再定義したり、“社会”の枠組みそのものにアプローチしていくんです。 松陰のすごさは、思想の先鋭さだけじゃないんですよ。「行動力」と「教育者としての愛情」、これらは僕の中で非常に大きい要素でした。 未来を生きる若者たちに、「お前はどう生きたいんだ?」と問うこと。それが教育であり、社会へのアプローチであり、命をかけるに値することなんだと教えられました。
住谷:まさに、吉田松陰の思想が、今の伊勢谷さんの根底にある“教育”や“仕組みづくり”の原点になっているわけですね。
伊勢谷:そう思います。僕が取り組んできたプロジェクトや、高校の設立も、「松陰先生だったらこういうとき何をするだろう」と問いかけながらやっている感覚があります。 死に方ではなく、生き方で示した人。それが吉田松陰だったと思います。 だから僕も、自分の仕事や言葉が誰かの“行動の引き金”になったらうれしい。 結果的に誰かが社会を変えるかもしれない。そのきっかけに、自分がなれたら本望だと思っています。
幸せとは「今に集中できる時間」を持つこと
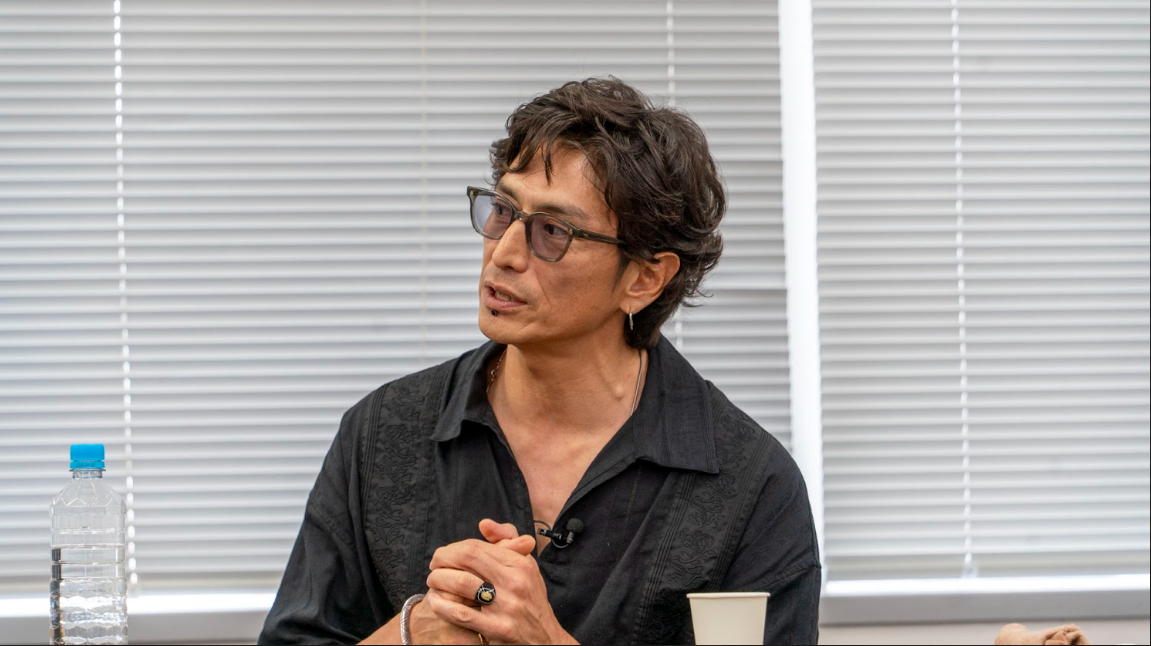
伊勢谷:幸せとは何かという話、よくされますよね。僕もここ4年間ぐらい、すごく考えました。 活動を制限された時期があったので、その中で「自分は何のために生きてるんだろう」と改めて向き合う時間がありました。 その中で気づいたのは、幸せには2種類あるということ。1つは「理性的な幸せ」。今の環境と自分の状態を比較して、「まあまあ悪くないな」と感じるタイプのもの。 そしてもう1つが「本能的な幸せ」。これはもっと直感的で、脳内物質が分泌されているような状態。 例えばサーフィンをしているとき、僕は「今ここ」に100%集中しています。そのとき、すごく満たされてるんですよね。 この“今に集中する”時間を、意識的に増やすことが大切なんじゃないかと思っています。 人によって出る脳内物質は違うと思うけど、自分がどの物質を好んでいるか調べてみるといいかもしれません。 それを人生の中でどう設計していくか。それも1つのライフデザインだと思っています。 僕が立ち上げた「ハッピーソース」も、そういう観点から生まれました。幸福の本質を、自分の体験からもう一度捉え直して、それを形にする。 SNSを活用して、誰かのペースではなく、自分のリズムで、好きなものを作る。そういう表現の自由が今は可能な時代です。 しかしそれを“ビジネス”として成立させるには、仕組みも必要です。だからこそ、アートとビジネスの交差点に立って、僕なりの形で社会に貢献したいと考えてきました。
「挫折禁止」――助け合う社会の設計へ

住谷:座右の銘なのかは分からないのですが、よくおっしゃっている「挫折禁止」という言葉はどこから出てきたのでしょうか。
伊勢谷:僕がすごく感動した言葉が「挫折禁止」です。 友人のドキュメンタリー監督が撮った、石垣島の高校のマーチングバンドの話で、そこに「挫折禁止」と書かれたホワイトボードがあったんです。 人数が少ないから、誰かが辞めると全体が成立しなくなる。だから「絶対に誰も挫折させない」と決めて、周りが支える。 僕はそれを聞いて「これが社会の理想の形だ」と思ったんですよ。 社会を変えるって、1人でできることじゃない。誰かが悩んでいたら、誰かが声をかけて、行動をフォローする。 その繰り返しが、結果的に「変わる力」になる。だから僕は、そういう社会の仕組みやデザインを考えたい。 学校を作ったり、アートを通じて社会にメッセージを発したり、すべてはその延長線上にあるんです。 もちろん、僕もすべてがうまくいってるわけじゃないです。ときには立ち止まりそうになることもある。 でも、そのときに「今、自分は何を大事にしたいのか」「何のために生きているのか」と立ち返ることで、もう一度前を向ける。それを続けていくしかないと思っています。
住谷:本当に、根底には「社会を良くしたい」という強い思いがあるんですね。
伊勢谷:ええ。正直、原体験があったわけじゃないんです。でも、だからこそ自分で「考えること」「答えを出すこと」「行動すること」をセットで実行し続けるしかないと思ってます。 どこかの誰かがいつか変えてくれるのを待つんじゃなくて、今の自分の行動が、未来の社会につながる。そう信じて進みます。
本記事は、ワクセル会議にて公開収録した伊勢谷さんのインタビューの内容です。
ワクセルのCollaboratorの方は、公開収録への参加が可能で、ご自身の事業へのヒントが得られる絶好の機会となりました。
ワクセルのCollaboratorの詳細は下記よりご確認ください。
https://waccel.com/collaboratormerit/
