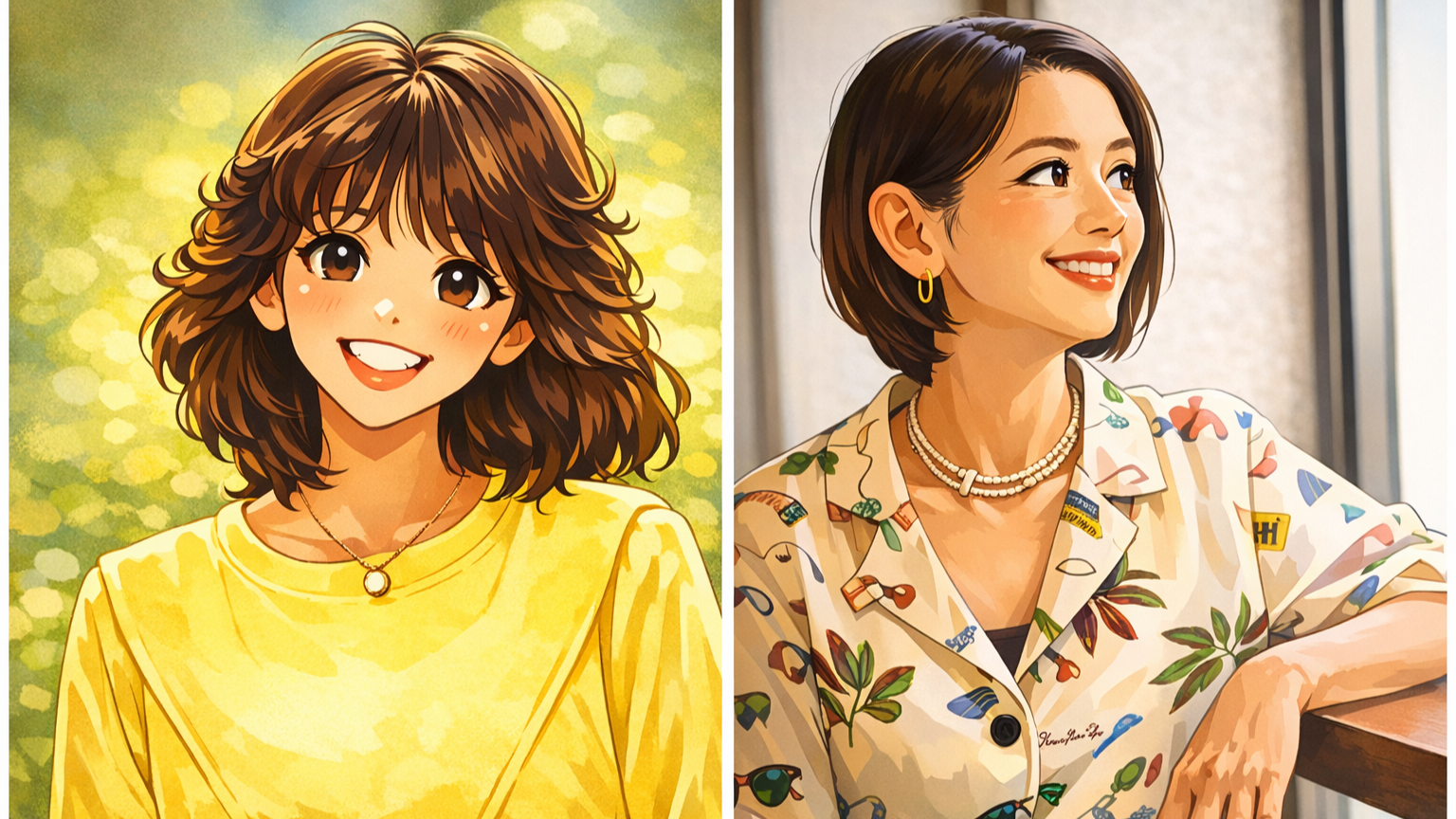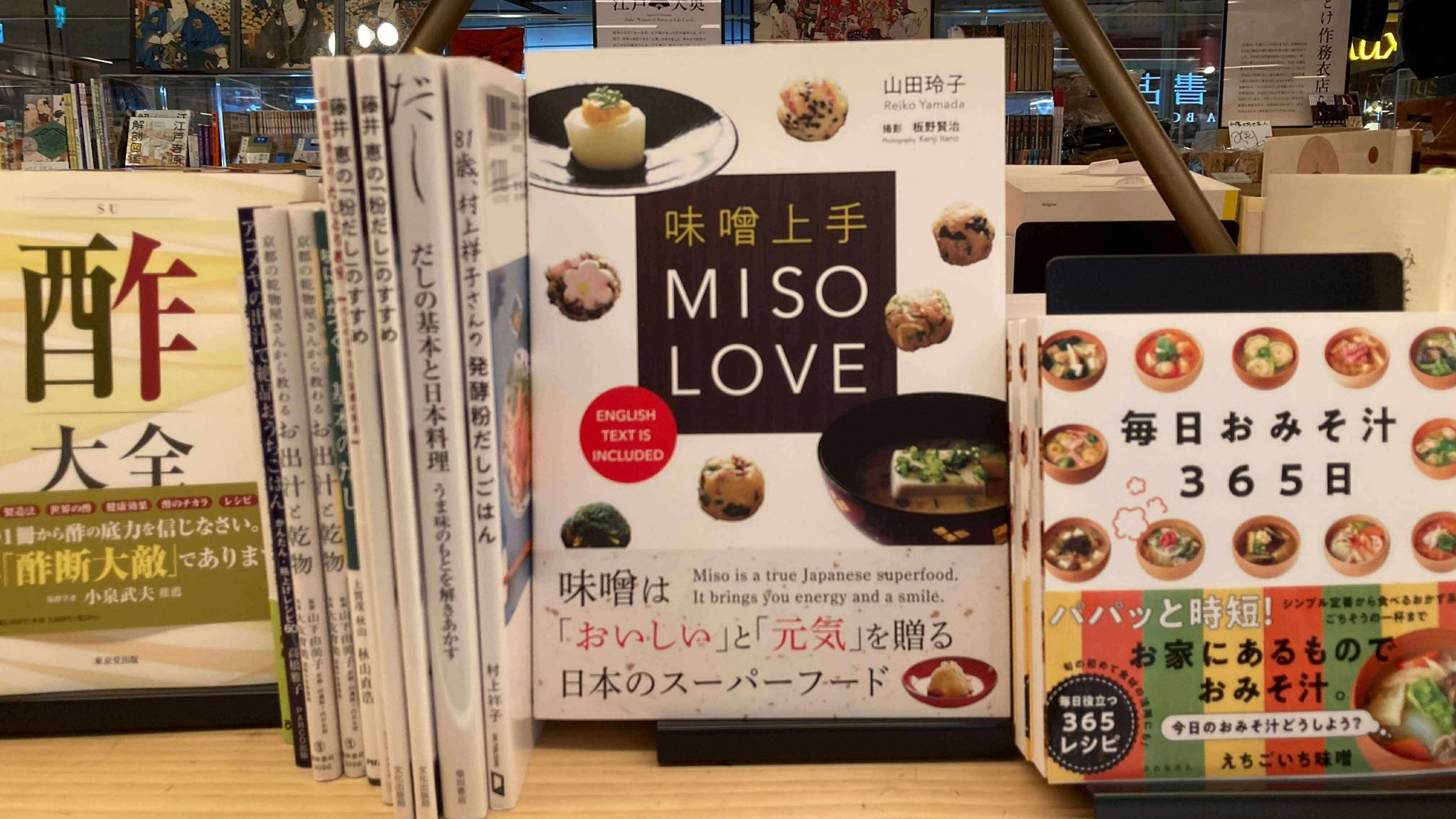パラレル活動が生み出す創造の起点

パラレル活動家Ⓡの岡田慶子(おかだけいこ)さんの連載コラムです。今回は岡田さん自身のご紹介です。仕事、家庭、地域、学び――そんな人の多面的な役割を前向きにとらえ、生き方を立体化する「パラレル活動」を提唱されています。ファシリテーター、ラジオDJ、プロフィールスタイリストや読み聞かせの活動など、いくつもの世界を行き来しながら人と人、経験と未来を“むすび、めぐらせ、ひらく”。その生き方の根底にあるのは、「誰もが創造の種を持っている」という強い信念でした。そんな岡田さんの想いを綴ります。
パラレル活動とは、“生き方を立体化すること”

私が提唱している「パラレル活動」とは、いくつもの仕事を同時にこなすことではありません。
むしろ、複数の軸で生きることで、視野を広げ、視座を自在に切り替え、経験を未来へ編み直していく生き方を指しています。
忙しさに流されているときほど、人は自分の軸を見失いがちです。けれど、日常の中に小さな“もう一つの顔”を持つことで、世界の見え方は少し変わります。
たとえば会社員でありながら地域の活動に関わること。
家庭を支えながらオンラインで学ぶこと。
その一つひとつが、自分の内側の世界を拡張してくれる。
そんな生き方を、私は「パラレル活動」と呼んでいます。
人は誰しも、ひとつの肩書きでは語りきれない多面性を持っています。
家庭人として、地域の一員として、学び手として、あるいは誰かの“推し”として。
そのすべてを「私の一部」として意識しながら生きること。
それこそが、パラレル活動の第一歩だと思っています。
交差する3つの軸 ― いま、私が動いている世界
この一年を振り返ると、今の私の活動は大きく3つの軸で広がっています。
【ひらく】― 人と組織、そして未来をひらく軸

大学の研究プロジェクトでは、会議のファシリテーションや運営支援を担当しています。
企業の組織開発プロジェクトでは、チームが自らの未来を描けるよう伴走しています。
また、自治体や協会等が主催するセミナーやイベントでは、司会進行やパネリストを務めています。
人と人、組織と社会を“つなぎ、ひらく”時間でもあります。
そして、リリース前の準備中である「セルカツ(自己紹介と動画づくりのプログラム)」は、まさに人を社会に「ひらく」ための実践支援だと考えています。自分の経験や想いを言葉にし、未来の自分を見出すこと。それが、誰かの次の一歩を支える力になる。 私はその過程に寄り添うことに、大きな喜びを感じています。
【むすぶ】― 言葉と感情、人と人をむすぶ軸

InterFMのラジオ番組を、10月から12月の1クール、DJ・インタビュアーとして人の物語を聴き、言葉を届ける機会を得ました。
また、企業の周年式典やライブイベントなどの仕事を続けながら、20年以上にわたりご依頼をいただいているオーケストラの司会・ナレーションにも携わっています。さらに、2年前からは子ども向けの読み聞かせボランティアにも参加しています。
いずれにしても、これらの現場では言葉だけでなく空気をデザインする力が問われます。アンパンマンの生みの親である、やなせたかしさんが言った「人生は喜ばせごっこ」。
同じ時間を共有する人たちをどれだけ喜ばせられるか、この挑戦が何とも言えない喜びで、いつも全力で楽しんでいます。
こうして誰かの心を動かす瞬間に立ち会うたびに、その喜びや学びが、また別の現場へとめぐっていくのを感じます。
【めぐらす】― 学びと気づきをめぐらせる軸

企業などでの研修や講演のほか、理事を務める熱中学園が展開する“大人のための社会塾”では、年に数回「先生役」でお話しする機会をいただいています。
「もういちど7歳の目で世界を…」を合言葉に、全国20数か所で展開されている熱中小学校では、自分の人生に新しいシフトを入れたいと集まる地域の方々との交流が、私自身にとっても大きな学びの時間になっています。
また、ユニキャリアとして展開する「未来航路塾」では、人生の折り返し地点に立つ方々と一緒に、これからの航路を描く対話を重ねています。想いや願望の言語化や行動化の支援だけでなく、壁打ちのようなアイデア対話などを5年近く続けています。
さらに、女性のからだを整える勉強会や専門家を招いた読書会など、関心のあるテーマをもとに学び合う場づくりも行っています。
こうした一連の活動は、学びは“伝える側”からだけでなく、“聴き合う反応”を通して自分にも還ってくる——そのめぐりこそ、人を成長させる原動力になるという信念で取り組んでいます。
経験が未来をひらく

様々な出来事、出会う人、そこで交わす会話の言葉。
声にならない多くの気づきが、別の現場の問いを生んでいきます。
これまでの年月を重ねてきたからこそ、あの時の出来事が今につながる瞬間がある。人との多様な関わりや情報が、思いがけないところで結びついていく。
活動の多さは混乱ではなく、共鳴です。それぞれの場での学びや気づきが響き合い、思考や感性の中に、新しい視点や発想が芽生えていきます。異なる世界が交わるとき、そこにまだ誰も見たことのない“何か”が生まれる。
その瞬間こそが、私にとっての創造の起点であり、次の未来をひらく力になっています。しかしながら、この“創造の起点”は、決して特別な人だけのものではありません。
誰もが自分の中に、小さなひらめきや感動の種を持っています。それを見逃さずに育てていくことが、未来をつくる第一歩なのだと思います。
パラレルに生きるということは、その種をいくつも持ち、どの瞬間にも“創造”が芽吹く自分でいること。
これからも、そんな生き方を楽しみながら続けていきたいと思います。