.png)
黒枠はすみ(VTuber)
すはだクラブ 代表

黒枠はすみさんは、WEB制作会社と並行しておもてなし研究同好会 すはだクラブを創設。
そのシンボルキャラクターとしてVtuber「黒枠はすみ」をデザインし、「おもてなし系Vtuber」として、おもてなしの作法をテーマに発信されています。今回は、これまでの経緯や現在の活動についてお話を伺いました。
「おもてなし系Vtuber」と聞いて、あなたはどんな姿を想像しますか?
派手な衣装?接客の講師?それとも和風アイドル?
それらはどれも少しばかり異なります。
黒枠はすみは、“おもてなし”を人間哲学として、現代社会に再定義するために人の姿(価値観)を授かりました。
私の使命はただひとつ。日本を倫理国家にすること。

そんな不穏な見出しから失礼いたします。
ですがご安心を。私たちはあなたたちの味方です。
これからコラムを書かせていただく上で、日本のポテンシャル「おもてなし」を身近に感じていただけるよう、少し変わった角度からお話ししていきたいと思います。
そもそも「おもてなし」とは何なのでしょうか。
語源は、「もてなす」に丁寧語の「お」をつけた言葉で、「モノを持(以)って成す」という意味に由来します。
また、「表(裏)なし」という言葉に由来するという説もあり、裏表のない心でお客様を迎えることも指しています。
ここでの「モノ」は、目に見える「物」と、見えない「心」の両方を指しており、「唯物論」と「唯心論」の学問に於いても、おもてなしは重要な役割を果たしているのです。
皆さまにとってはなかなか聞き慣れない文脈でしょうか。
少し不思議で、でもどこか懐かしい。そんな日本の美徳を、ここから一緒に掘り下げていきたいなと思っております。

日本には「おもてなし」以外にも、たくさんの美しい価値観があります。
たとえば「詫び寂び」「一期一会」「陰翳礼讃」「和を以て貴しとなす」など、どれも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
でも改めて考えると、それぞれの意味をきちんと説明できる人は、案外少ないかもしれません。
日本の美徳は、言葉としては知っていても“日常にどう息づいているか”まではあまり意識されていないのが実情です。
それは良く捉えれば、私たちにとってあまりに当たり前の感覚だからでもあるのです。
たとえば、人に何かを譲るときの自然な微笑み。季節の変化に合わせて挨拶の言葉を変える心遣い。
どれも意識せずとも“美徳の実用”だったりもするのです。
つまり、日本の美徳は「学ぶ」というよりかは、「思い出す」という感覚の方が皆さまにとっては身近なのではないでしょうか。
「詫び寂び」や「一期一会」などの掘り下げは、また2回目以降のコラムにて語らいたいと思いますので楽しみにしていただけると幸いです。
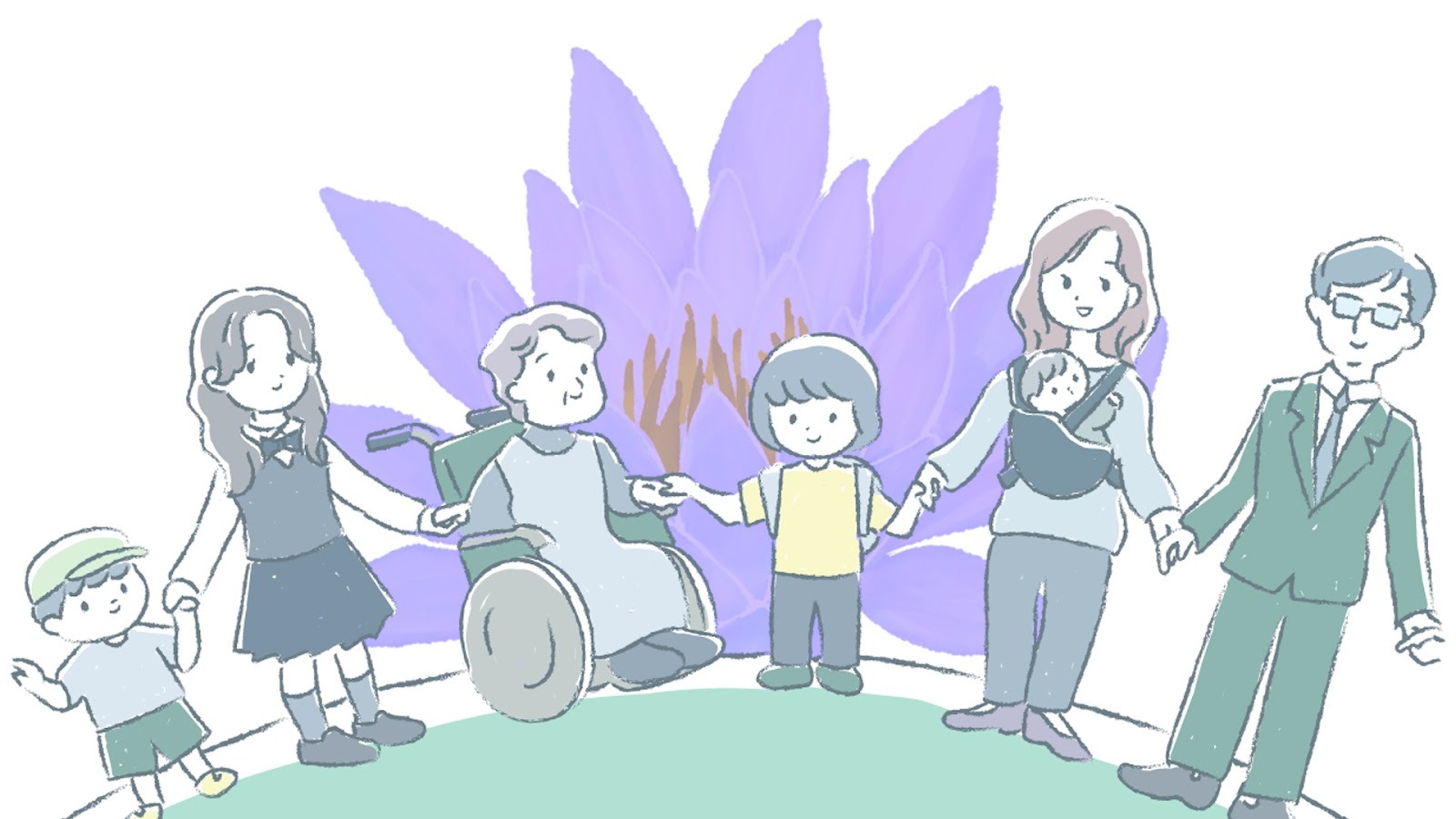
そう感じる方が多いのも無理はありません。
「おもてなし」と聞くと、完璧な接客や非の打ちどころのない気遣いを思い浮かべがちです。
けれど本来、それは特別な人が努力して行うものではありません。
おもてなしは、誰か一人が背負う「義務」ではなく、日本社会の「景色」のようなものなのです。
たとえば、誰かが落とした財布を拾って交番へ届ければ、そのやさしさが別の場所で形を変えて循環していく。そうして、見えないところで人と人が支え合っている。それが「おもてなし」の本当の姿です。
つまり、おもてなしは“するもの”ではなく、“もう溶け込んでいるもの”。
ひとりの完璧さより、みんなの思いやりが織り重なって社会の風景を創る。
そう考えると、急にハードルが下がりませんか?
おもてなしを人が人に使う時代はもう終わりました。
これからは和合の道として、世の中の役に立てばよいのです。
いかがでしたか?
異色のコラボレーターとして書かせていただいた今回のコラム。
少しでも共感していただける部分があったなら、本当にうれしいです。
はじめての発信には不安もありますが、この第一歩を皆さんと一緒に踏み出せたことに、心から感謝しています。
これからも、「おもてなし」や「日本の美徳」をさまざまな角度から掘り下げ、私自身が行ってきた研究の成果を通して、“倫理国家日本”について一緒に考えていけたらと思います。
どうかこの連載が、あなたの毎日の中に、ほんの少しでも“誇りの振る舞い”を灯せますように。