
経営戦略コンサルタント/大学教員
名和田 竜 × 住谷知厚
名和田竜(なわたりょう)さんは、起業家として数々の事業に挑戦しながら、人材育成や教育にも力を注いでいます。 本インタビューでは、起業の原点や目的、逆算思考によるロードマップの描き方、「ベストワン」である考え方まで、実体験を交えて語っていただきました。 若手の育成や未来への教育に対する熱い思い、ビジネス戦略のヒントとともに、経済的な成果だけでなく心の成長も重視する名和田さんの思考をまとめます。
ビジネスの原点と起業のきっかけ
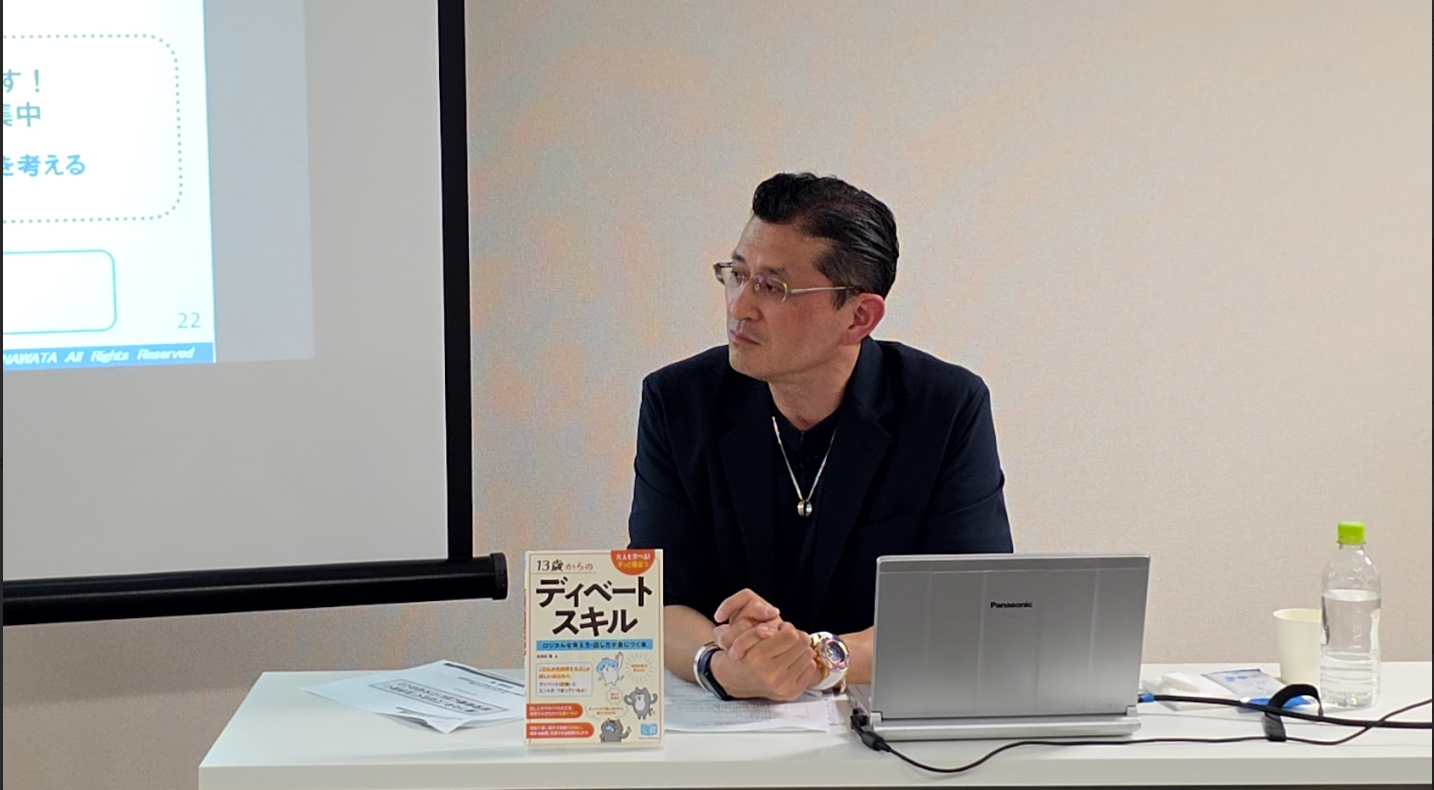
住谷:最初に、起業のきっかけについて、聞かせてください。
名和田:自分が独立したのは、準備万端だったからではありません。 勢いで飛び出した側面が強いです。大学を出て広告代理店でセールスプロモーションやマーケティングに携わり、 現場での戦術は得意でした。仕事自体は楽しかったです。ただ、顧客の本当の課題を解くためには、 現場の戦術だけでなく川上の戦略が必要だと感じるようになりました。会社の中で「戦略を提案する部門を作りたい」と打診して、 社内プレゼンで一度は承認を得ました。しかし、会社のルールでは役員会の承認が必要で、結果的に「兼務なら許可する」と言われた。 若かった私は「兼務はめんどくさい」と思い、そのまま独立してしまったのです。 結果的にはリーマンショックが来て、本当に厳しい時期を経験しました。もしあと一年遅れていたら、起業していなかったかもしれません。 そうした苦しい局面もありましたが、逆に震災後の復興期には東北や新潟で中小企業の支援に呼ばれ、実戦の場が増えました。 あの時期は忙しく、学びも多かったです。
独立の背景には、もう1つ動機がありました。本を出すことで「名刺代わり」にしたいという思いです。 最初に出したのは、自分へのマーケティングに関する本で、外部に自分の考えを示すためでした。 実績が乏しい時期でも、文章があれば客観的に伝わります。後にディベートやランチェスター戦略についても書きました。 特にディベートについては、大学でコミュニケーション論を教えている経験から、 若い世代に短期間で論理的思考や表現力を身につけさせられると実感していたことや、出版社からも話があって、 13歳からの読者向けに柔らかく書こうと決めました。
起業の話に戻ると、勢いで飛び出したとはいえ、そこで得た経験が今の核になっています。 現場での苦労、厳しい市場環境、復興支援の現場での実践的な教育。これらが合わさって、私の目的が固まってきました。 端的に言えば「人にワクワクを届けること」です。 MCとしての役割もそうですし、コンサルタントや講師として人を育てるという意味も含めています。 ターゲットは当初曖昧でした。多くの情報を浅く拾っていた時期もありました。 今は「誰に」「何を届けるのか」を明確にする重要性を強く感じています。 船で例えれば、目的地を定めないまま出航しても、風に流されるだけです。 目的を定めることで、準備すべきスキルや出会うべき人、押さえるべき資源が見えてきます。 これが起業の原点であり、今も変わらない出発点です。
逆算思考とロードマップ
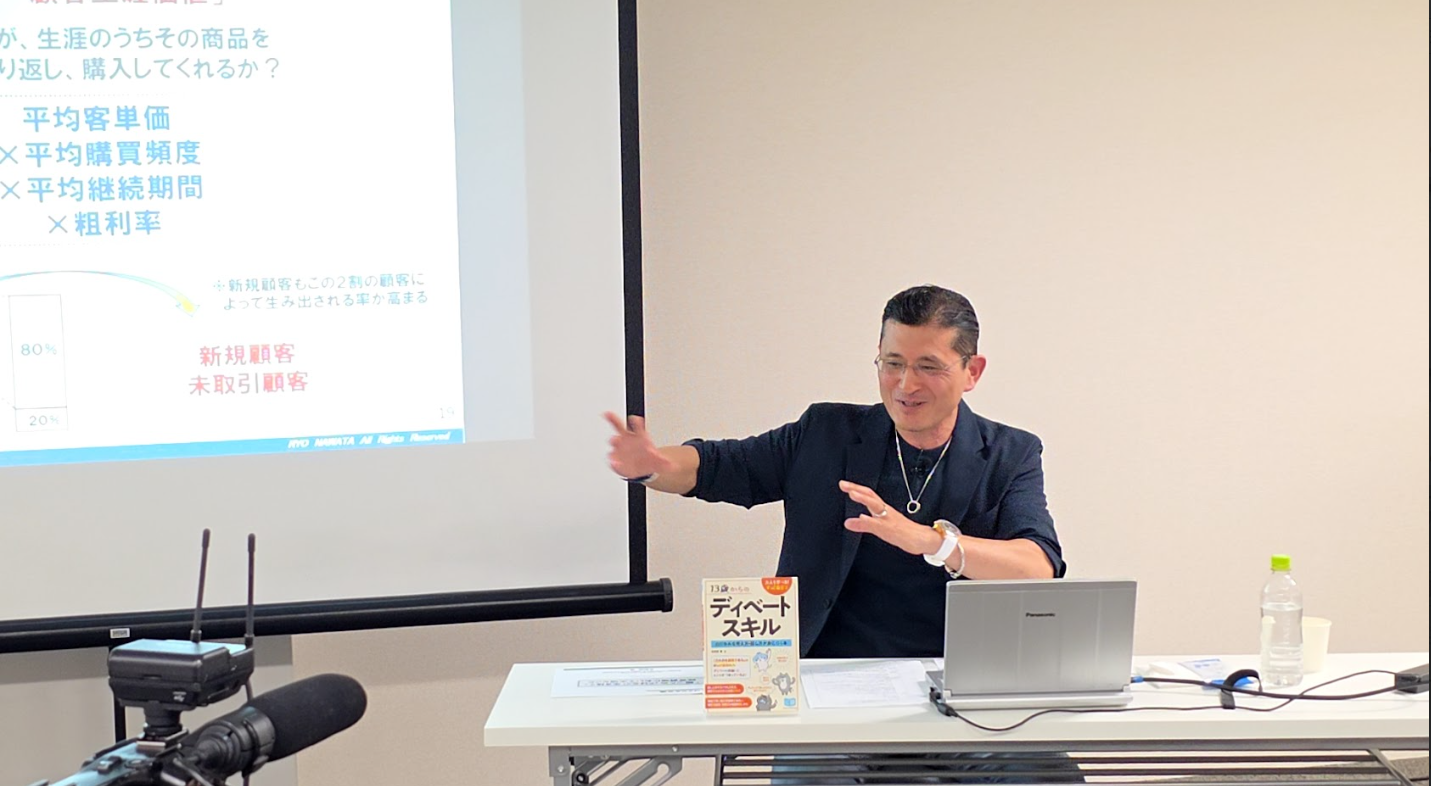
住谷:目的が明確になったら、具体的な進め方はどう考えればよいですか。
名和田:まず「目的」「現状」「ギャップ」を紙に書き出すことです。 目的はなぜ起業したのか、会社や事業で何を達成したいのかを一行で表現します。 現状は今の実力や状況。売上やスキル、人脈、資金、提供価値の可視化です。 目的と現状の差がギャップです。このギャップを埋めるのが戦略であり、マーケティング活動です。
実務ではワンシートで戦略を作ることを勧めています。ワンシートの項目はシンプルで良い。 現状、課題、本来あるべき姿、ギャップ、方向性、具体施策、実行の難易度と期待効果です。 方向性を複数出したうえで、具体施策を洗い出します。施策ごとに「実行難易度」と「期待できる効果」を縦横にマッピングする。 そこで見えてくるのは着手すべき優先順位です。高効果で低難度なものから着手します。 効果が高いが難度も高ければ、分解して短期で実現可能な小さな施策に分ける。
ワークの場では、参加者同士でアイデアを出し合い、評価軸を共有することが大切です。 なぜなら、目標の共有がないと「やらされ感」だけが残り、モチベーションが下がるからです。 共有されれば自発的な提案が生まれます。組織であれば、このワンシートを全員で回覧し、なぜこれをやるのかを腹落ちさせる。 ここで得られる効果は大きいです。
時間軸の設定も不可欠です。3年後の到達点を定め、そこから逆算して1年、半年、3か月のマイルストーンを置きます。 その逆算をさらに日々のタスクに落とし込みます。逆算思考があると、日々の小さな活動が目的に結びつきます。 もし1年後に達成していなければ、何が足りなかったのかを検証し、PDCAを回す。 ここで重要なのは、期待効果と難易度を定量化することです。曖昧なままだと判断がぶれます。
最後に、現場で実行する人の育成です。戦略を書いただけでは何も変わりません。 現場のプレーヤーが理解し、自分ごととして動けるかが分かれ道です。 だからこそ、ワークや研修でスキルとマインドを同時に育てる。 小さな成功体験を積ませ、次のチャレンジに繋げていく。この活動の積み重ねがロードマップの確度を上げます。
「人を育てる」ことが経営の核心
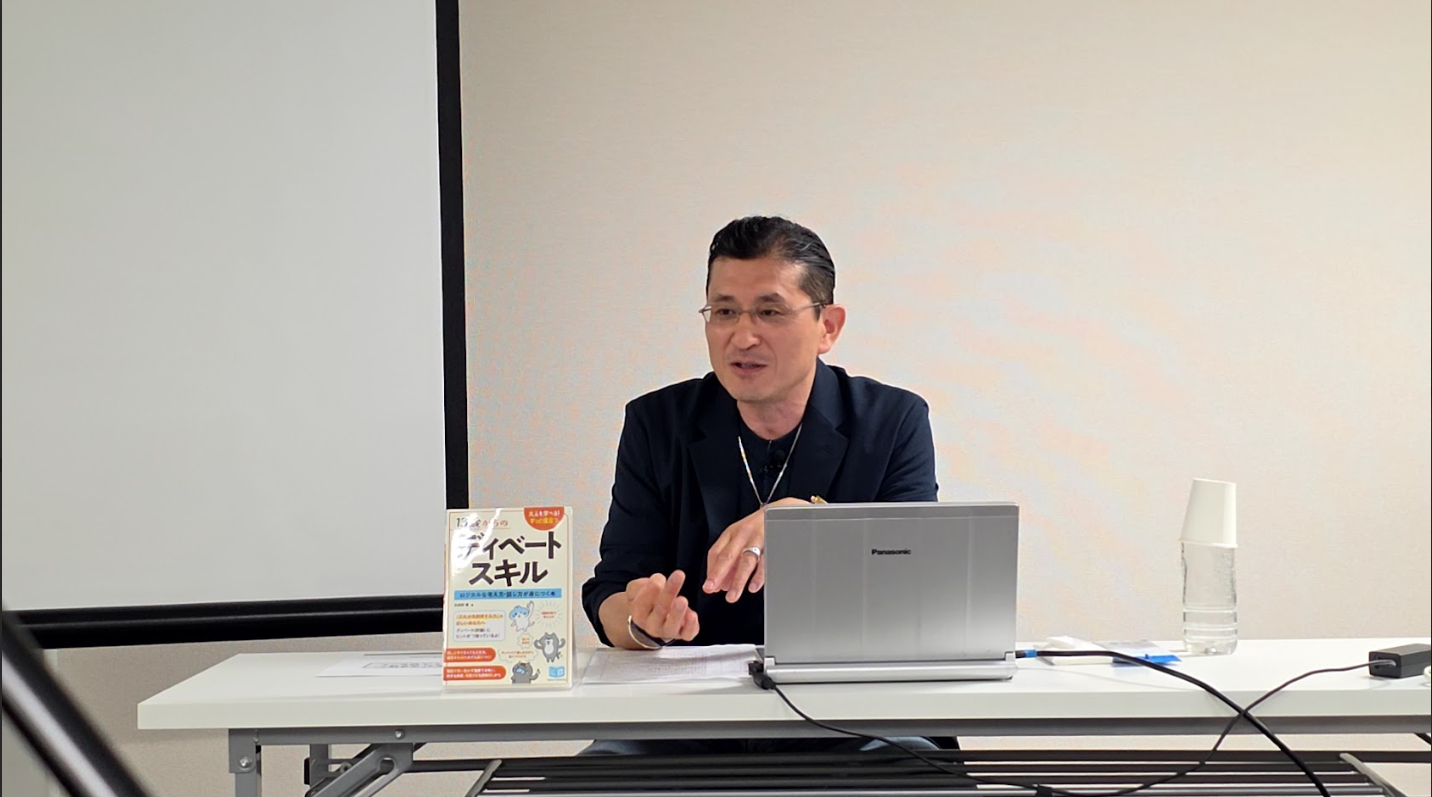
住谷:経営において、人材育成は重要だとおっしゃっていますが、具体的にどのように考えていますか?
名和田:経営者の方に指導させていただいているテーマとして、「生き抜く」ことが非常に大事であるとしています。 コロナ以降の世の中の変化として、テクノロジーと価値観の変化は皆さんも感じていることと思います。 前提としてたルールが変化し、今までと同じような市場のパイではなくなっています。市場に対してのシェアには種類があります。 マーケットシェアは市場占有率。顧客シェアは既存顧客の中での占有。マインドシェアは顧客の頭の中でどれだけ認知されているか。 これらは従来の重要指標です。最近さらに重要になっているのがハートシェア、つまり顧客の心の中に入り込む度合いです。 頭で「知っている」だけでは価格や利便性で揺らぎます。 心で「好きだ」「これがいい」と思ってもらえれば、価格差や条件変化に左右されにくくなります。
また、変化に対応して新しい市場価値を生み出した具体例の1つに富士フィルムが有ります。 フィルムの素材技術を化粧品や医療機器に応用して新たな市場を作りました。 ガラケーは逆に独自進化に偏り、世界基準から置き去りになった。 メルカリはリサイクル業界から顧客を奪っただけでなく、若者のスマホ時間の一部を「取る」発想で新たなパイを作りました。 ここに示されるのは「市場の見方」を変える力です。そこからは、ハートシェアをいかに掴んでいくかです。
ハートシェアを掴むには接触率だけを上げてもダメです。接触は親近感を生む一方で、頻度が高すぎると嫌悪感に変わります。 重要なのは「好意度」です。好意度を育てながら接触と認知を設計する。 SNSでの接点、顧客対応、商品体験、イベント参加などのタッチポイントを通じて心に残る体験を作る。 スノーピークのコミュニティや、クラフトビールのファンづくりはその典型です。コアなファンが新規顧客を連れてくる循環が生まれます。
ビジネス観点では、「パレートの法則」を忘れてはいけません。売上の多くは少数のコア顧客が作ります。 ここで「ベストワン」の考え方を私はしています。ナンバーワンやオンリーワンではなく、顧客にとってのベストワンであること。 代替品が出ても揺るがない関係性を築ければ、そのコア顧客が新しい顧客を連れてきてくれます。これが持続可能な循環です。
最後に人の育成との結びつきです。ハートシェアを作るための接点は、最終的に現場の人間の振る舞いで決まります。 電話対応、接客、企画の伝え方、イベントでのホスピタリティ。ここに共感を生む技術と心構えが必要です。 だから経営の本質は人を育てることに立ち返ります。心に残る対応をする人を育てれば、ハートシェアは自然と高まります。 人材育成とマーケティングは車の両輪です。
若い世代への教育と未来の展望
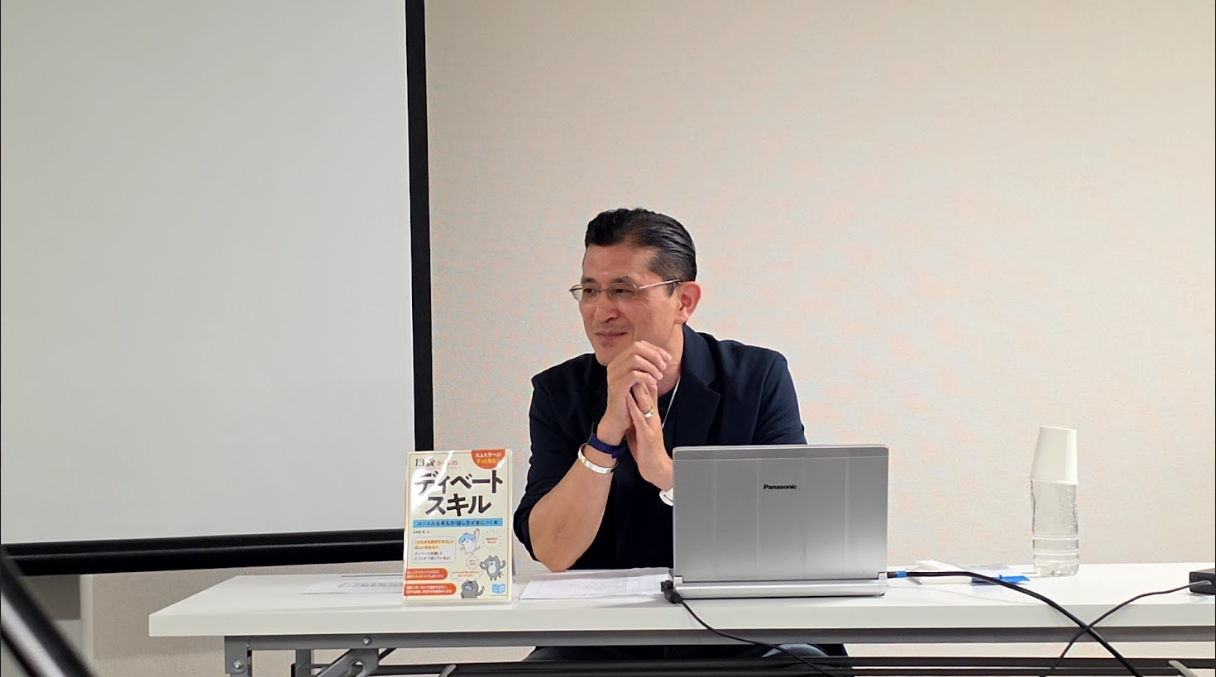
住谷:今後の活動での取り組みと期待を聞かせてください。
名和田:今、私は大学での授業に力を入れています。 学生に教えるのは知識だけではなく、「どのように考え、どう動くか」です。 社会に出れば、知識は重要ですが、それ以上に思考力や行動力が問われます。 その点においてディベートによる教育は効果があります。 ディベートは自分と異なる立場を理解し、客観的に論を組み立てる訓練です。 これにより視野が広がり、多様な価値観と対話できる力が身につきます。
中学・高校の段階からこうした力を育てたいと考えています。 若い頃に論理的に考える習慣がつくと、将来の進路選択や起業、チームワークに大きな差が出ます。 大学では「負けないスキル」をキーワードに授業を組み、プレゼンや実践課題を通じて成長体験を重ねてもらいます。 これが私のミッションの一部です。
企業向けには、人材教育を通じて組織が自走する仕組み作りを支援しています。 研修で終わらせず、現場での実行力を育てることに注力します。 新人が育ち、次世代が育つことで企業は持続的に強くなります。 人材育成は人件費ではなく投資です。ここに経営資源を回す判断が重要です。
将来的には、教育と実践をつなぐ場作りを進めたいです。 学生と企業が協働で課題解決するプログラムや、地域と連携したプロジェクト。 実践の場が若い人の学びを加速させます。 目的は一つです。次の世代が自分で考え、行動し、周囲を巻き込める力を持つこと。 これが社会を変える起点になります。私自身はこれからも教育の現場に立ち続け、若い人たちと一緒に挑戦していきます。
■名和田 竜さん コラボレーターページ 公式HP
本記事は、ワクセル会議にて公開収録した名和田さんのインタビューの内容です。 ワクセルのCollaboratorの方は、公開収録への参加が可能で、ご自身の事業へのヒントが得られる絶好の機会となりました。 ワクセルのCollaboratorの詳細は下記よりご確認ください。
https://waccel.com/collaboratormerit/
