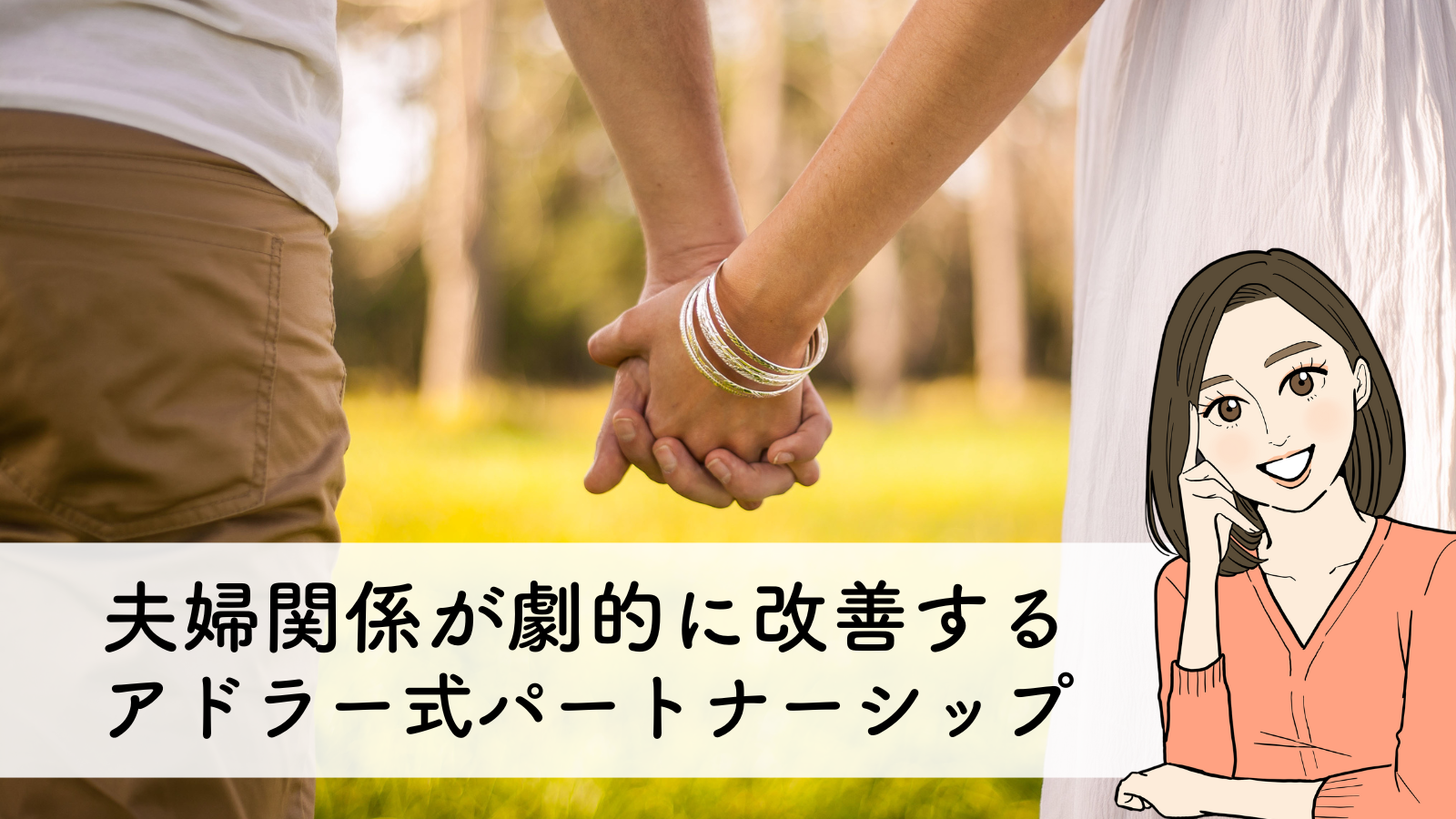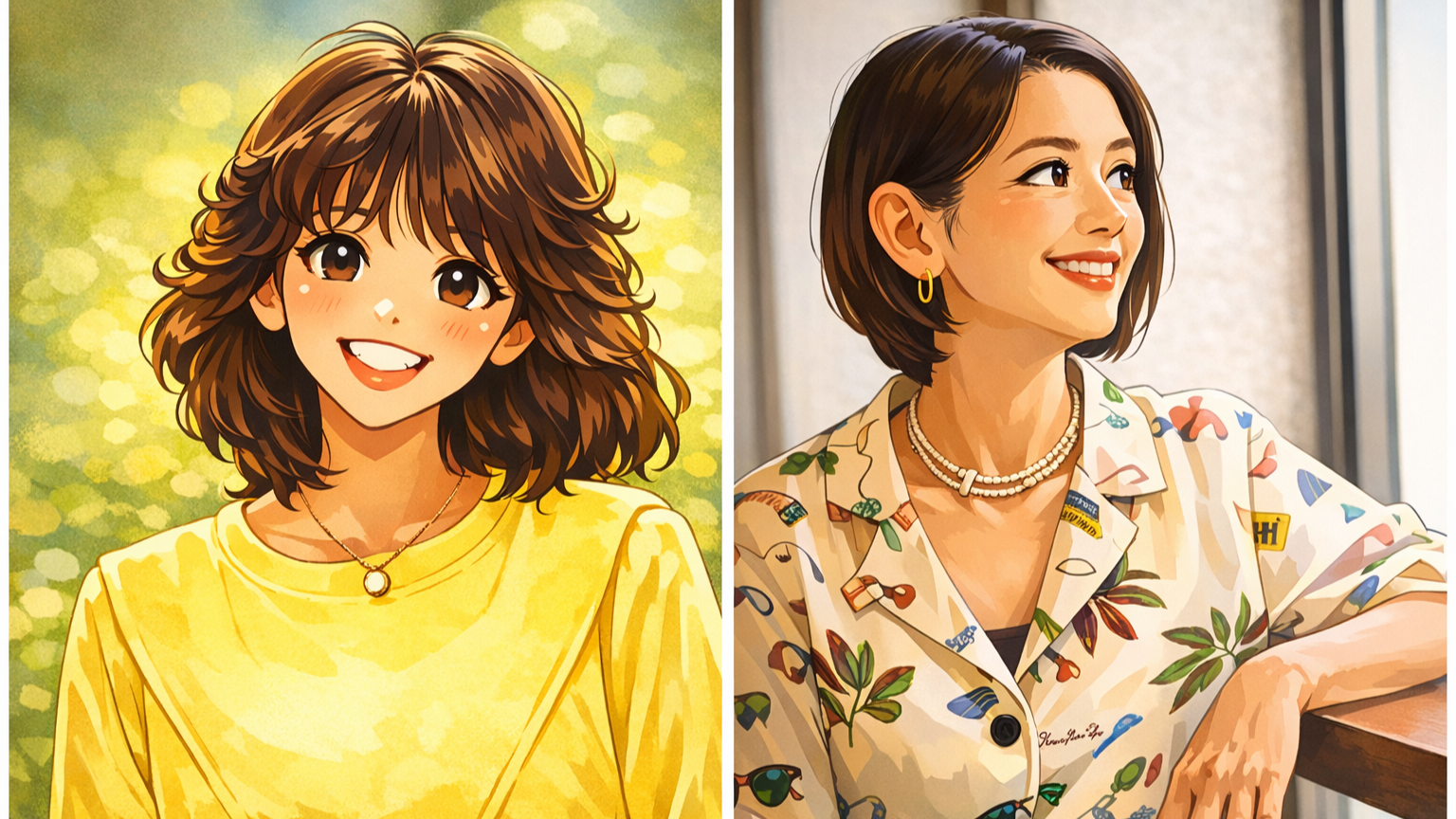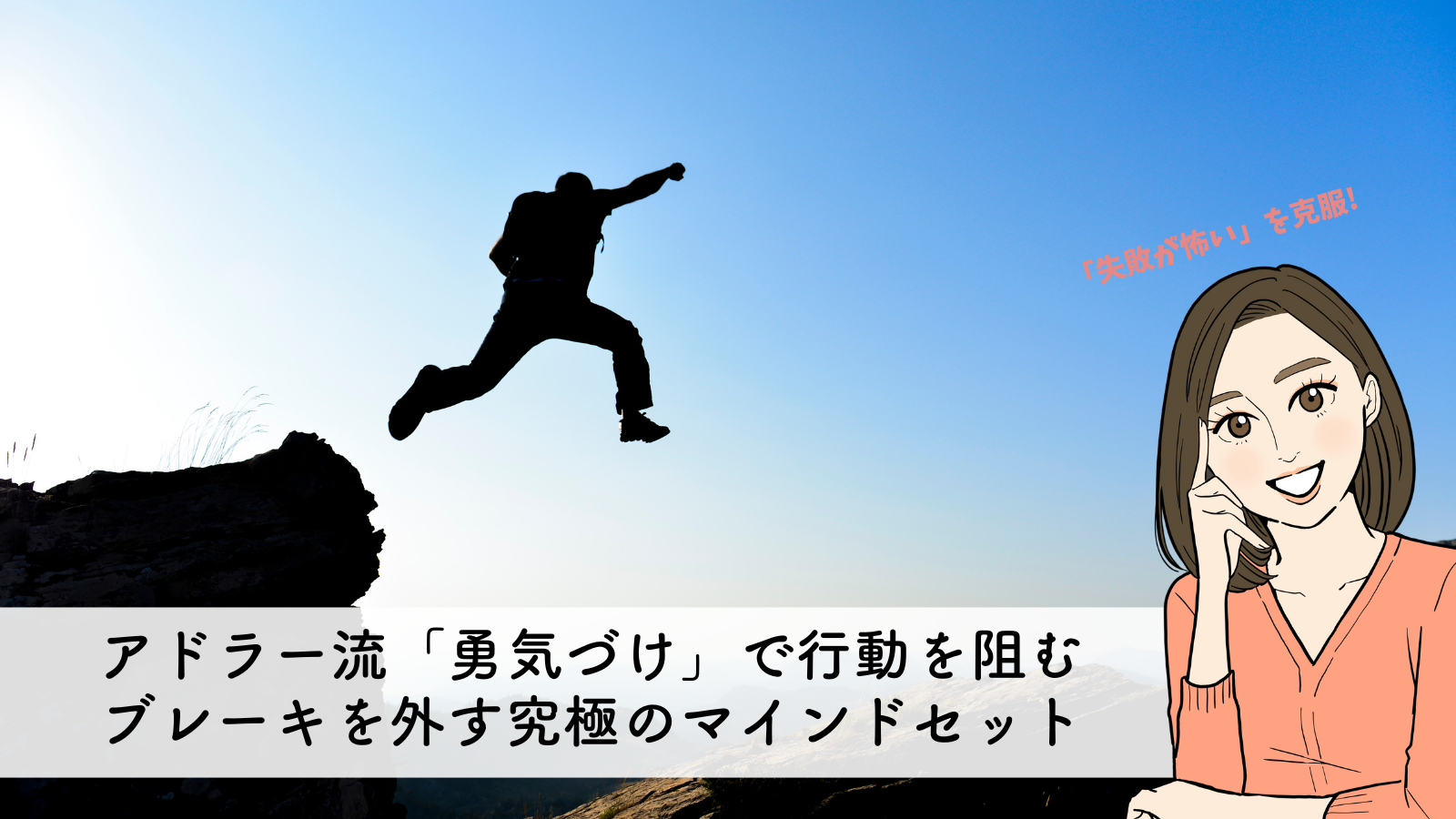「人とペットがより良く暮らせる社会を目指して」メディアを巻き込んで奮闘する女性の軌跡
テレビ番組の制作に長く携わられている傍ら、保護犬の問題に取り組む澤田祥江(さわたさちえ)さん。テレビ業界に入ったきっかけと保護犬の活動を始めた経緯、今後の展望を伺いました。
テレビ業界でドラマよりドラマティックなドキュメンタリー番組を制作
もともとは舞台俳優になりたくて大学在学中、劇団に所属していました。片桐はいりさんと舞台で共演したこともあります。ただ、役者として生計を立てるのは難しく、稽古や舞台本番が始まるとアルバイトもあまり入れない状態。それでも役者として生きていきたいと思った私は、文学座の求人募集を見て、制作部に入社しました。女性は結婚したら仕事を辞めるというイメージが強い時代。私は女性でも手に職を付けたいと思っていて、『ものづくり』というテーマが外せませんでした。私が思う『ものづくり』は形がないものを形にしていくこと。偶然にもテレビ関係で仕事をしている知り合いからテレビの番組制作の仕事が合っているのではないかと言われて、テレビ業界に入ることになりました。
テレビ番組制作の仕事はADからスタート。お芝居の経験を生かしてドラマ部に入りたかったのですが、当時28歳だった私はドラマ部だと年齢的に遅いということと女性という理由から、報道部に配属になりました。ドキュメンタリーを作るのが主な仕事で、障がい者スポーツの選手に密着取材させていただいたことがあります。その取材を通してドラマよりドラマチックで面白いと感じたんです。下世話な言い方をすると「テレビのものです」と言えば、人の人生にずかずかと入って行けますよね(笑)。その人を深く掘り下げて世の中に伝えることにやりがいを感じました。ADを3〜4年経験した後にディレクターになります。
文学座で働いていたときは女性蔑視の風潮がありました。テレビ局は女性が社会で活躍するのが一握りの時代でも露骨な女性差別はありません。もし文学座を続けていたらお芝居の関係者としか付き合いがなくなりますが、テレビだとテレビ関係ではない業種の方とも知り合えます。業務内容は大変ですが、テレビ局の仕事の方が私の性格に合っているなと思いました。
ホストクラブの密着取材企画でディレクターデビューをしたんです。年齢を考えると周りの人がやらないようなことをやらないといけないと思っていました。仕事ですといってどこにでも入れることが、この仕事の醍醐味だと思ったからです。テレビ取材という力を使って、普通では入れないところに全部入ってやろうと考えました(笑)。ホストクラブや風俗に行き、俳優の東ちづるさんと日本全国の刑務所の取材にも行きました。私が興味のある場所はほとんど入りましたね。
動物番組がきっかけでペットの問題と向き合うように
現在、テレビ業界に入って20年以上が経ちました。私が所属している企画実現部という部署がテレビ以外のことを行う部署です。企業の動画制作、書籍のプロデュースや映像化する際のキャスティング、テレビの制作にまつわることを一手に引き受けています。そこで私は企画を考える営業担当をしていました。もともと動物に触ることができなかったのですが、私の企画が通って『動物病院24時』という密着取材をすることになりました。最初は犬やネコが好きではなかったのですが、取材しているうちに救急で運ばれてくるワンちゃんやネコちゃんに家族以上の愛情を持っていました。ワンちゃん・ネコちゃんに関する問題に向き合うには、きちんと触れ合えるようになる必要があるなと感じたので、なでるようになり、触るようになり、気付けば私もワンちゃんを家族として迎え入れたいと思うようになります。
取材中に知り合って保護したヨークシャー・テリアがきっかけで獣医師さんと知り合うことができ、現在取り組んでいる事業のひとつである獣医師さんのプロデュースにつながっています。獣医師の方とテレビの企画ではなく、ペットたちのためになる活動ができると良いねという話をしていました。
今は保護犬を飼っているという方も多いと思うのですが、10年前は保護犬が認知されておらず、病気を持っているとか汚いとか悪いイメージを持つ方が多かったんです。その悪いイメージを変えたいと思い、保護犬にまつわる活動を始めました。この活動は自分でも保護犬を飼っているので、趣味と実益を兼ねている上に、メディアの仕事にもつながっています。ボランティア活動と仕事がつながっているので楽しいなと感じます。
保護犬の認知拡大により人もペットも幸せな社会に
ワンちゃん・ネコちゃんたちを迎え入れるのも手放すのも人間です。ワンちゃんの異常行動のほとんどは人間が原因です。嫌なことをされたらほえる、ほえてもダメなら噛むことになります。ペットを飼うときに我々が自分のライフスタイルと飼う動物の性質などをきちんと考えているかどうかが大切です。かわいいと人気のトイ・プードルーー時々「トイプードルは噛まない」という声を聞きますが、噛むという行為自体はあります。噛むということを頭に入れておいて、噛まないためにはどうしたら良いのかということを犬種の性質に合わせて知っておく必要があります。何も考えずにぬいぐるみのようにペットを飼う人が多くいるということが問題だと思うのです。
そして、その問題を生んでいるのがペットに関わる人やその関係者の人たちです。ペットショップ同士で競争や対立をしていたり、揉めるのはいつでも人間関係です。人間のもめごとはペットたちには関係ありません。あの人が嫌だから、考え方が違うからといって、批判だけはするものの、相手を理解しようとしない。たとえば、私たちがペットの性質を知ってから飼いましょうという啓蒙活動をしても、その意見に寄り添えない、他の団体からは批判だけをされてしまう。この繰り返しでは、いつになっても一つにまとまらない。そうなると、この問題は解決しないと思うんです。
あと、命ある犬や猫が法律上では「もの扱い」なのも疑問に感じます。私たちはペットに関する教育も大切ですが、まずは法律を変えて欲しいと訴えています。たとえば、私がワンちゃんを飼っていて、お散歩中にワンちゃんが小さな子どもを噛んでしまったとします。その傷が深くて子どもが亡くなってしまったとしたら、私が殺人罪で捕まって刑務所に入らなくてはいけません。一方で、小さい子どもに殴られてうちのワンちゃんが亡くなってしまった場合には器物破損になるだけです。動物愛護法が改正されてきましたが、まだ不十分と言えます。ものとして飼う人が減らないのは法律上でものとして扱われているからなんです。私はメディアの人間なので、こうしたことの疑問やペットの認知を広げるのが私の役割かなと思っています。そうすることで人間と動物のより良い暮らしが実現できるのではないでしょうか。
保護犬のことをたくさんの人に知ってもらうために、ボランティアでイベントをプロデュースをすることで皆さんに保護犬のことをもっと知ってもらいたいですね。メディアとしての立場としてはペットの番組を作りたいです。以前に作っていたこともあるのですが、時代的に早すぎたみたいですね。あとは、ペットブームの今だからこそ、獣医医療ドラマの原作などの番組を作って、保護犬の問題解決につながればいいなと思います。