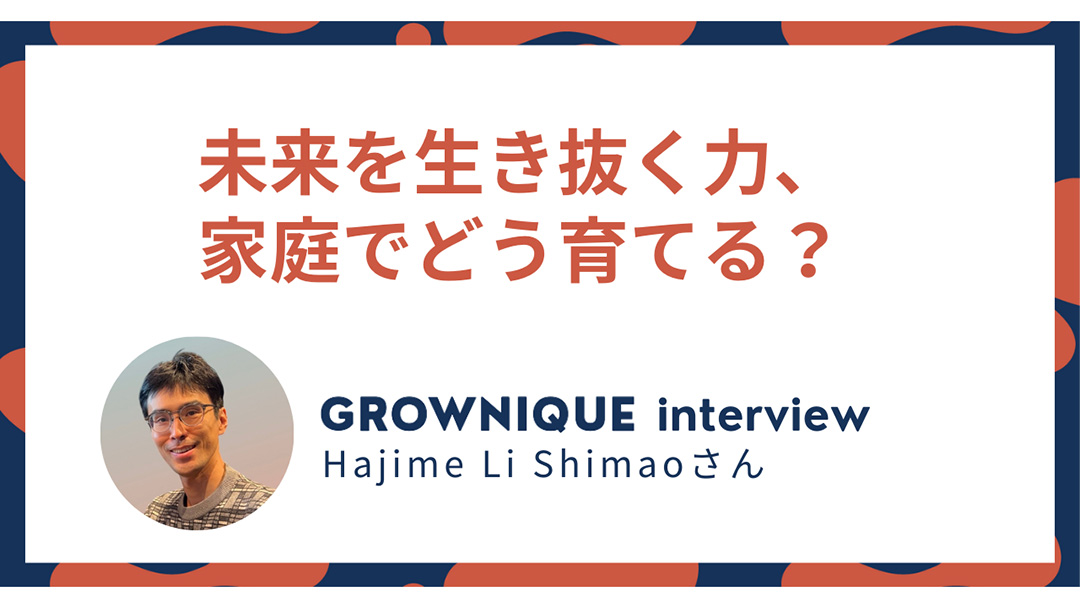AGIの時代、教育の「当たり前」はどう変わる? ~「いい大学→いい会社」の時代は終わる?~
教育の目的や常識は、時代とともに変化してきました。
近年は「いい大学に入って、いい会社に就職する」が成功のモデルのひとつとされてきましたが、AIがさらに進化し、AGI(汎用人工知能:人間のようにさまざまなタスクを柔軟にこなすAI)の時代には、そのモデルは通用しなくなるかもしれません。
今回も引き続き、ペンシルバニア州立大学助教 Hajime Li Shimaoさんとともに、教育の役割や価値観の変遷をふまえ、「子どもの教育に、これから親としてどう向き合うべきか」を考えます。
1-1. 教育の歴史を振り返ると見えてくる、今の『当たり前』の変化
島尾:みんなで教育の歴史を軽くおさらいしましょう。変革の時代には歴史の勉強が大事です。
加藤:これからを考えるために、まずは歴史から始める必要があるんですね。
島尾:はい。歴史を遡って、どのように今の「当たり前」ができたのかを把握しないと、今の「当たり前」が永遠に続くような気がしてしまい、選択を誤りかねません。
加藤:なるほど。子どもの教育は数十年先を見据える必要がありますもんね。
島尾:歴史を見通すと、「時代によって実は大きく変わりうるもの」と「それでも人類にとって普遍的なパターン」がちょっと見えてくるんです。
加藤:歴史といっても膨大ですが、ポイントとなるのはどのあたりですか?
島尾:さまざまな側面があり地域によっても大きく異なりますが…
たとえば、
- 古代ギリシャ(アテネ)では、民主制を支えるために自由民の教養が大切にされていました。一方で、いわゆる「労働」は(たとえばアリストテレスなどによって)価値が低いものとみなされ、多くを奴隷が担っていました。現代人の「教育はその後の労働力の価値を高めるためのもの」という認識とはずいぶん違います。
- 中世から近世にかけて、貴族や富裕層が私的に受けていた教育が、生徒や教師を組合化することで大学が誕生しました。高等教育によって労働者の価値を高める、いわゆるHuman Capitalモデルで説明されるような世界観は今でこそ当たり前になっていますが、産業革命によって技術労働者が必要になって以降に本格化したものだと思います。
加藤:大学の役割は時代によって変化してきましたよね。
島尾:現在の大学は、学術研究・教養教育・職業教育の三役を担っています。いわゆるフンボルト型大学というもので、19世紀前半に急速に発展したシステムです。しかし、仮に産業革命級の変化が再び起これば、極端な話、この大学の在り方自体が失われても不思議ではありません。
加藤:AIによる世の中の変化は、産業革命級といっても過言ではないですよね。
島尾:そう思います。そして、労働の歴史も一度おさらいしておくと良いと思います。「仕事を自ら選択し」「その仕事で自己実現をする」みたいな発想がこれほど一般になったのもごくごく最近のものですから。
加藤:そう考えると、今のさまざまな「当たり前」はすぐに変わりそうですね。
1-2. 教育と労働が切り離された時代、教養はなぜ大切なのか?
島尾:AGIの可能性で世の中が激変しているわけですが、「AIを使う側になって収入を得よう」といった最近よく見られる言説はせいぜいこれから20年、2045年くらいまでの話な可能性があることには要注意だと思います。現役世代はそれでいいのですが、子供たちはその先を生きることになります。
加藤:確かにそうですね。今の子どもたちが現役世代を迎える頃には変わることになりますね。
島尾:生産性と労働賃金が今後どのように変化していくかについて議論がなされています。もちろん現時点ではどんな予測も推測の域を出ませんが、一つの例をご紹介しましょう。
加藤:解説お願いします。
島尾:横線が時間で、縦線は左が生産性で右が労働賃金。青線は今までの世界がずっと続いた場合で、黄色と赤はAIによってどう変わるか。赤は本当に世の中が劇的に変わった場合のシミュレーションです。生産性はAIのおかげでどんどん伸びますが、賃金はあるところをピークにむしろ下がり始めるんです。つまり、AIの発展により生産性は向上しても、労働者の賃金が上がるとは限らないということです。
加藤:ということは、「将来豊かな暮らしができるように、良い教育を与えて、良い仕事に就いて…」が崩壊するということですね。
島尾:そうなります。教育と労働のリンクが切れ、労働と収入のリンクも切れるかも、ということです。
加藤:そうすると、教育はどういう位置づけになるのでしょうか。
島尾:それでも、教育の重要性は変わらないと考えています。たとえば民主主義は、教育なしには成立しません。1867年、イギリスの政治家ロバート・ロウは『私たちは自分たちの主人(市民)を教育しなくてはならない』と語り、義務教育の必要性を訴えました。
加藤:コメニウスも「人を人らしくする(秩序)のは教育」といってますね。
島尾:そうです、まさに。そしてなにより、働く必要性が低下したら、教養がないと面白くない。人生の充実度を左右するのは「何を知っているか」「何に興味があるか」といった教養の部分になります。
加藤:「教養」というのが大切になるんですね。
島尾:人間にはコミュニティが必要で、自分のコミュニティをつくるためにも教養が必要です。自分自身のアイデンティティ形成のためにも教育は必要です。加えて、どれだけAIが発展しても、自分の人生の意思決定は自分でやることになります。教育を通して「意思決定」できるようになる必要があります。結婚相手までAIに決めてもらうわけにはいきませんからね。
加藤:教育の重要性はなくならないということですね。
島尾:そうです。インターネットが出てきたときに「知識の価格はゼロになる」「コンテンツにお金を払う人はいなくなる」という言説があったけどそうはならなかったですよね。「必要とされる知識の種類が変わる」「無料のコンテンツが溢れる中でそれでもお金が取れるコンテンツに人が集まるようになる」という変化だった。今回も「知性の価格はゼロになる」と言っている人がいるけど、必ずしも教育の重要性はなくならないかもしれない。
1-3. 親世代と子どもの時代、必要なスキルはどう変わる?
加藤:子どもの教育にどう向き合うか、親としてもマインドセットをこれまでとは大きく変える必要がありそうですね。
島尾:そうですね。労働経済学の知見、特にHuman Capital Theory、『教育は高収入に直結する』という考え方は、AI時代には当てはまらなくなるかもしれません。「偏差値の高い大学にいくと就職に有利」「理系の方が文系より就職がいい」みたいな発想を子供に押し付ける時代ではないと思います。
加藤:就職を前提にした教育は意味がないということですね。
島尾:少なくとも、「2025年現在の労働市場を前提とした就職戦略」を元に教育を考えるのは、子供世代にとっては意味がないんじゃないかと思います。たとえば、アメリカの失業率は比較的低くて雇用自体は堅調ですが、一方でハーバード大学でMBAをとった学生が卒業後の就職が見つけられず苦労している、と言うWall Street Journalの記事が最近話題になりました。つまり「良い大学を出れば就けると想像されていたホワイトカラーの仕事」が減っているのかもしれません。大手テック企業の大型レイオフのニュースも多いですよね。
加藤:日本は2010年からずっと売り手市場が続いていますが、あとを追いそうですね。
島尾:先に述べたように、労働と収入の関係が変われば、国民全員に一律で生活資金を配るベーシックインカムのような新しい社会保障制度が必要になってくるかもしれません。
もし仮に「そんな中でも、子供には労働でお金を稼いで欲しい」ということであれば、「機械でもやれるけどなんとなく人間にやっていて欲しい仕事」か「機械より人間の方が安い仕事」を想定するのがよいというのが僕の個人的な意見です。
前者はたとえばスポーツ選手などが好例ですよね。メッシよりサッカーの上手いロボットが出てきたとしても、私たちは人間のサッカーを観たいと思うはずです。これはチェスや将棋では既に起こっていることです。
そこまで競争率の高い職種でなくても、レストランのウェイターや学校の先生、カウンセラーや医師、福祉や介護、法律関係などは「人間にやってほしい」という要求が残るのではないかと思います。
後者はロボット系の技術の進展次第なので読めない部分もありますが、たとえば電気設備技術者なんかは機械化するのはかなり高コストですよね。ソフトウェアは一度開発に成功すれば一気にスケールアップできるけれど、ハードウェアが必要な仕事はロボット製造の単価が毎回かかるわけですから。
加藤:仕事に関しての価値観が激変しそうです。
島尾:たとえば、「将来の夢は?」と言ってなりたい職業を聞くのはいますぐやめたほうが良いと僕は思います。どんな職業が20年後に存在するのか大人にとってすら未知数ですからね。まして子供は50年後にも生きなくてはいけない。
加藤:日本人の大人は仕事がアイデンティティの人も多いですが、それも変わりますね。
島尾:だから、「どうありたいか」「何をしているときが一番楽しいか」「何に時間を使いたいか」が大切になっていきますよ。「たとえお金がもらえなくても、やりたいと思えること」を子どもと丁寧に考えるのがいいと思います。ボランティアでもいいし、地球温暖化を解決するでもいい。
加藤:収入と労働が必ずしも直結しない時代には、単に「お金を稼ぐための仕事」ではなく、自分が価値を感じる活動を見つけることが大切ということですね。
親としては、子どもが学び続けて、教養を身に着けるために、どのような環境を整えるべきかを考えることが重要となりそうです。具体的にどのような教育投資や選択をすれば未来に備えることができるのか?今後、そのポイントをお伺いしていきたいと思います。