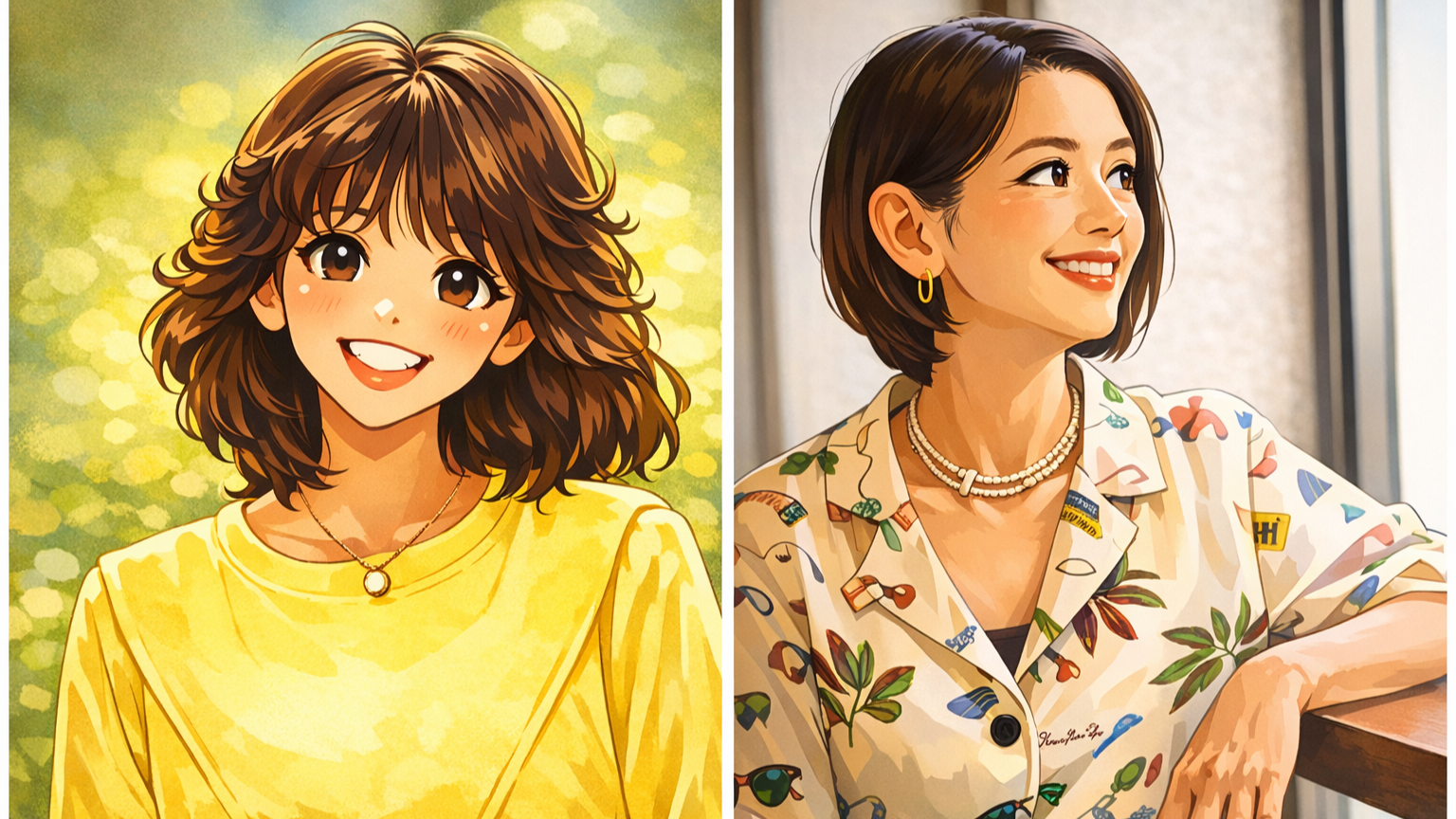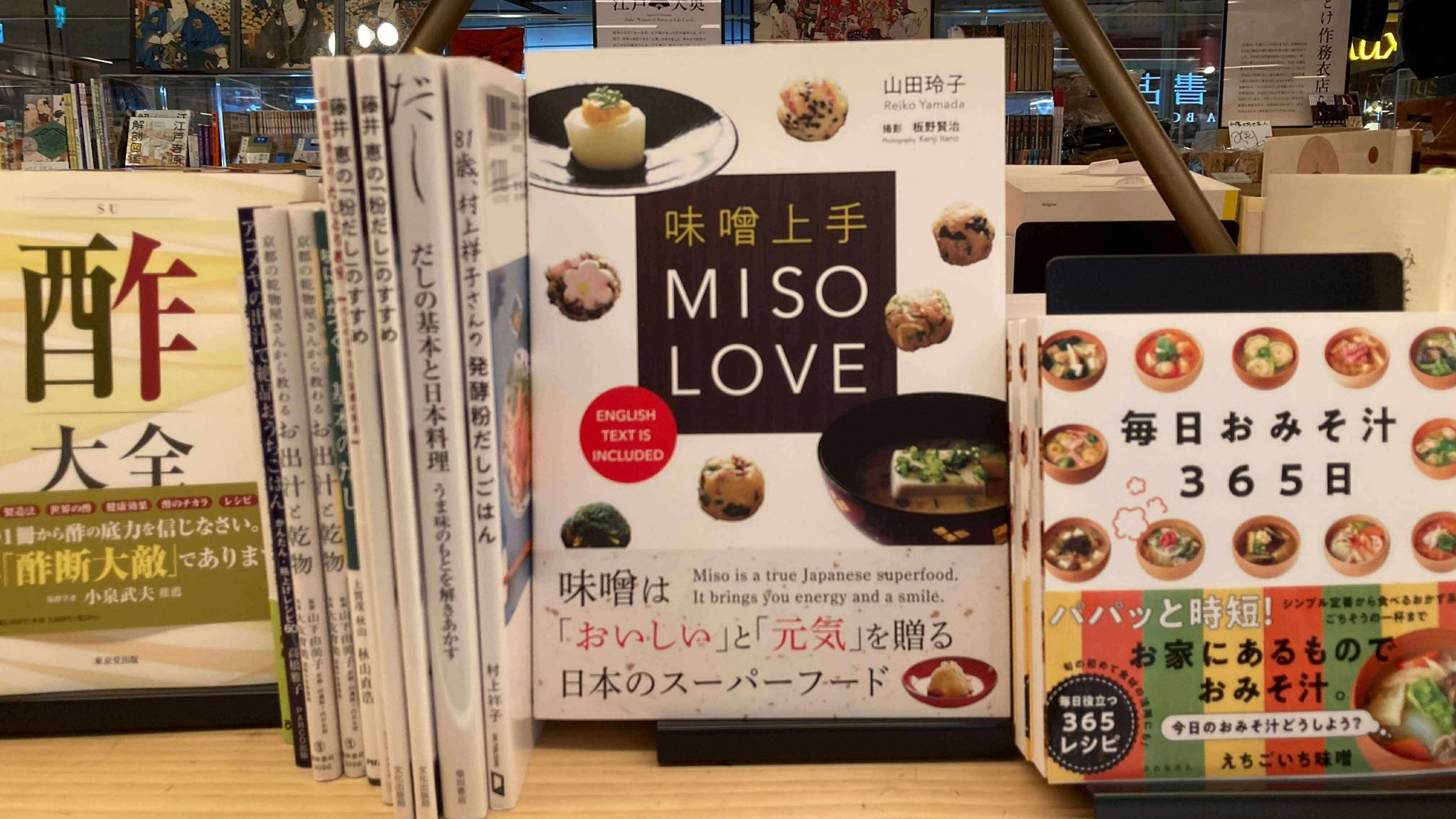易経を軸に広がる探求――田中重光さんの活動
「ボディ、マインド&スピリットの調和、東洋哲学(易経、密教、禅)、健康(バイオハック、WHM)、ICT、教育、音楽などインテグラルライフを遊行中。」
今回は、このような自己紹介を掲げる会社員・田中重光(たなかしげみつ)さんの活動についてご紹介します。
私が田中さんと出会ったのは、『余白珈琲』という交流の場でした。ここは、”貨幣の価値だけではなく、人とのつながりや共感の循環を重視する経済圏を築こうとする共感資本の考え方”を掲げる『eumo』というコミュニティで学んだ人々が集う場。メンバーではない私が『余白珈琲』に招かれた日、偶然隣り合わせたのが田中さんでした。
易経を通じた知の継承
その日、彼の最も関心を寄せる「易経(えききょう)」というものを初めて知りました。中国に古くから伝わる四柱推命などよりも歴史が古く、五千年前から存在するとされる易経に魅了され、田中さんは学びを深める中で、ある行動を起こしました。それは、絶版になった易経に関する書籍の復刊。
「素晴らしい書籍なのに、古書しかなく手に入れるのが困難で、しかも難解な文体。学びたいと考える縁ある人に手に取ってもらい、後世に残していきたい」
こんな思いで明治時代の易経の第一人者・根本通明の講義書をAmazonで出版したというのです。Amazonで検索すると、『周易(易経)講義』や『老子講義』など、彼が復刊した書籍が並んでいました。
その後、田中さんが年に一度だけ開催する『冬至占(とうじせん)』という占いを通じた易経解説のオンラインセミナーに参加する機会を得ました。冬至占は、1年の節目に自身のテーマや未来の方向性を見つめ直すものとのこと。
この経験を通じて、易経が単なる古典の知識ではなく、実生活の指針として活かせることを実感しました。こうしたセミナーやワークショップの開催は、経済的な利益を目的としたものではなく、易経を「知ってほしい」「活かしてほしい」という純粋な思いだけで開催しているとのこと。さらに、本セミナーでは田中さんによる誘導瞑想も行われ、彼の知識が幅広い領域にわたることが伺えました。
教育への探究心とグリーンスクール訪問
先日、田中さんはバリ島のグリーンスクールを訪問していました。ここは2008年に設立された国際的な学校で、世界中から集まった生徒たちに自然と調和した学びの場を提供し、持続可能な社会を築くためのリーダーを育成することを目指していると、開校当時から話題の学校です。彼が易経を通じて探究するのは、単なる知識の習得ではなく、学びをどのように社会に活かすかという視点です。日本に必要な教育への強い問題意識を持つ田中さんは、日本でのグリーンスクール設立検討プロジェクトの一環で参画したようです。
実践を通じた探究心
バイオハック機器を見るだけに高知を訪ねたり、新年には神社での大寒禊(みそぎ)に挑戦したりと、SNSで垣間見る彼の行動は、まさにパラレル活動を実践する人の姿勢そのものです。
・興味が湧いたらすぐに行動する
・考えるだけでなく、まず動いてみる
・複数の視点を持つ
・新しい出会いを大切にする
・答えがなくても挑戦し続ける
普回向(ふえこう)の精神
田中さんは、「易経」という人としての在り方の軸を持ちながら、学びを深め、健康や教育といった多様なテーマに積極的にかかわり続けています。多岐にわたる活動を続ける中で、どこに彼の原動力があるのか。
そんな問いを投げかけると、田中さんはこう答えました。「最近はあまり突き詰めて考えてなくて楽しい、興味の向くままにだけれど、テーマや共通性はあると思っています。普遍性、人、インテグラルとかシステムとか全体性。でも、やっぱり健康第一、健体康心が人としては望ましい姿なので、それを目指しているし、そういう情報を発信したら喜ぶ人もいるだろう、というモチベーションなのかな。」
そして、続けて言いました。
「お経にある『普回向』という言葉のとおり、功徳を積んだら人に分ける。そうありたいと思っています。」
田中さんの言葉には、彼の行動の根底にある「知を分かち合う」精神がありました。学びや経験を自分だけのものにせず、広く共有し、人とのつながりを大切にする姿勢。それが、彼をさまざまな地へ導き、多様な出会いを生み出しているように思います。