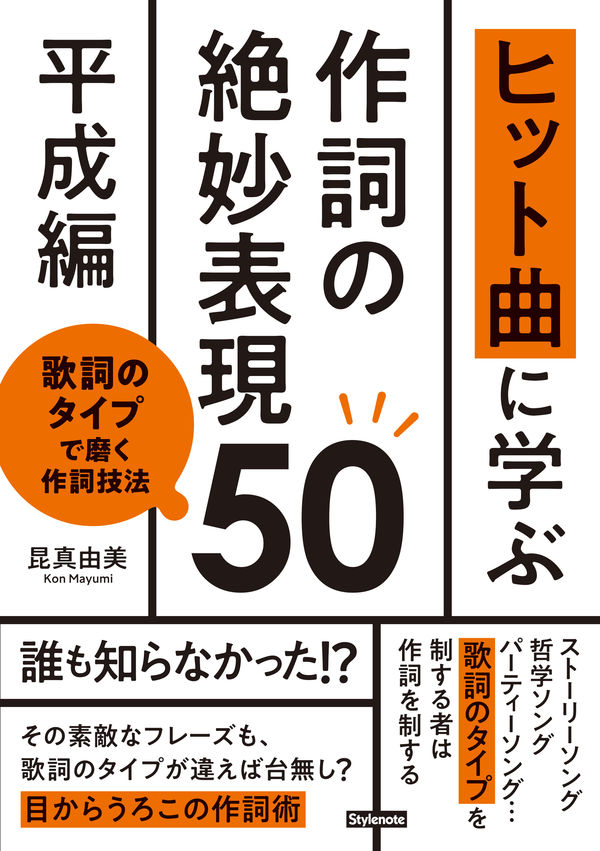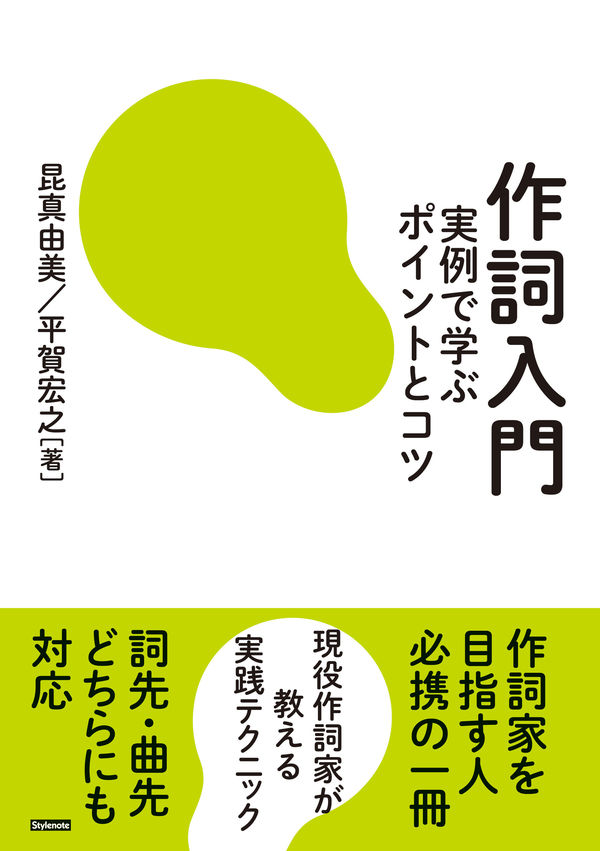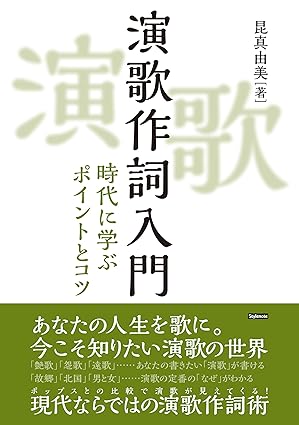
演歌作詞入門
時代に学ぶポイントとコツ
現代の視点から演歌をとらえた、新しい演歌の作詞入門書。演歌が流行した時代背景をもとに歌詞の特徴を掘り下げ、ポップスとの違いとともに解説。さまざまな演歌ならではの作詞技法を新たな切り口で実践的に学べる一冊。
演歌の歌詞が書けるようになる、実践的な作詞入門書。演歌が流行した時代と背景、ジャンルの立ち位置などを踏まえ、歴史を紐解きながら、演歌の歌詞の特徴を学ぶ。ポップスを中心に作詞をする現役の作詞家・作詞講師である著者が、ポップスとの違いを交えつつ、演歌特有の作詞方法を解説。現代の視点から新たな切り口で作詞術を展開する。「プロット作成」や「推敲」、効果的な「表現技法」など、演歌の作詞に欠かせないポイントのほか、演歌の3つの要素「艶歌」「縁歌」「俺歌」と、3つのタイプ「遠歌」「炎歌」「怨歌」を軸にした、著者ならではの作詞へのアプローチも紹介。演歌の歴史を学びながら演歌の作詞術が身につく一冊。
「演歌とはどんな歌?」と聞かれたら、皆さんはなんと答えるでしょうか。
古い歌?
昔からある歌?
なんだか物悲しい歌?
着物を着て歌う歌?
こぶしを効かせて歌う歌?
どれも正解のようで、しかしどれも演歌のすべてを表現できていない気がします。そして、演歌がいったい何であるのかを考えると同時に、「歌謡曲とは何か?」という疑問も浮かんできます。演歌の定義、演歌と歌謡曲の違いなどを調べてみても、しっくりくる答えにはなかなか辿り着けません。演歌と歌謡曲の定義はどうやら非常に曖昧なようです。
作詞の授業で、演歌や歌謡曲の歌詞を添削する機会がたびたびあります。2022 年に出版した『作詞入門』では、ポップスを基軸とした作詞方法について解説していますが、演歌や歌謡曲となるとまた異なる作詞方法が必要に思えました。令和である今も「演歌」というジャンルはありますし、演歌の新曲は途絶えることなくリリースされています。また、演歌の歌詞を書いてみたいという声もよく耳にします。
演歌が流行していた時代に演歌の歌詞を書くことと、令和の現代に演歌の歌詞を書くことは、異なるアプローチが必要なのではないか。そして、現代のポップスとの違いを確認しながら演歌の作詞方法を見出すことは、令和の今だからこそできる面白い試みなのではないかと思い、本書を執筆するに至りました。
本書は、令和の時代に、演歌の歌詞を書くことを目指した本です。昭和や平成の時代では見えてこなかった発見がきっとあるはずです。
さあ、演歌の歌詞の世界をともに紐解いていきましょう。